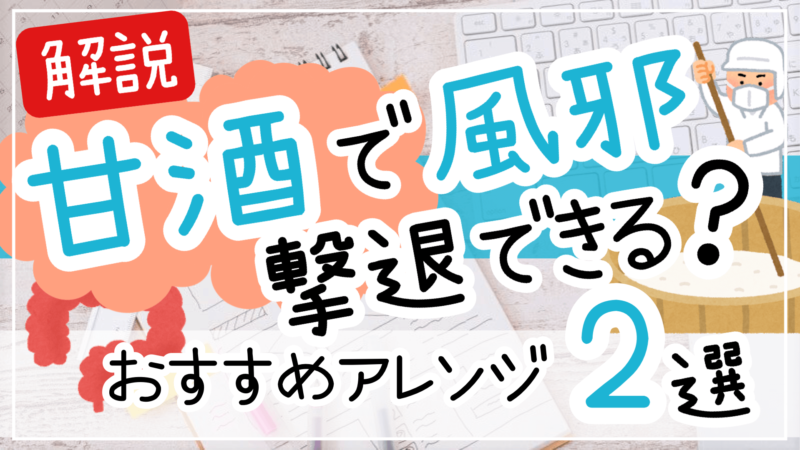【この記事で解決できるお悩み】
・風邪予防に甘酒が良いって言われるのはなぜ?
・体調がすぐれない時のおすすめの飲み方やアレンジ法をおしえて!



この記事では、こんなお悩みを解決します!
「飲む点滴」と言われるほど、栄養価の高さが注目されている甘酒。
体調を整えるため、そして風邪をひかない丈夫な体を作るために、甘酒を飲み始める人が増えています。
そして、多くの方が「風邪を引かなくなった」「免疫力が上がった」と、甘酒の効果にびっくりしているみたい。
でも、なぜ甘酒は風邪予防に効果があるのでしょうか?
今回はその理由を徹底解説!
さらに甘酒の風邪予防効果を高めるためのおすすめの飲み方やアレンジ法も整理してみました。
発酵を体系的に勉強したくなったら…
発酵ライフ推進協会オンライン校へ
\仕事に繋がる無料サポートもたくさん(*´ω`*)/


この記事を書いた人:
腸活研究家 長谷川ろみ
発酵食品にハマり、ダイエットなしで12㎏減。痩せたことをきっかけに腸を愛でる生活に目覚める。重度の便秘から解放され、腸活研究家として活動開始。今では発酵ライフ推進協会通信校校長を務め、昔の自分と同じ悩みを持つ方に向けて腸や菌のおもしろさを発信中。詳しくはこちら
甘酒が風邪予防になる理由


甘酒が風邪の予防をする理由は、以下の3つです。
一つずつ見ていきましょう。
栄養の吸収率が良いから
甘酒は「飲む点滴」と言われるほど、たくさんの栄養素がバランスよく含まれています。
特に多いと言われる栄養素は、体のエネルギー源となるブドウ糖やオリゴ糖、体内では作ることができない必須アミノ酸、代謝を高めるビタミンB群です。
ブドウ糖
オリゴ糖
必須アミノ酸
ビタミンB群など
しかし、甘酒がすごいのは、そのたくさんの栄養素を分解してくれる麹菌をセットで摂取できること。
麹菌は100種類以上の酵素(ハサミのようなもの)を持ち、さまざまな栄養素を細かく分解するという特徴がある菌なのです。
こんなにたくさんの種類の酵素を持つ菌はなかなかいません。



麹菌は酵素バサミの使い手なんです!
普通の食べ物はわたしたちの胃や腸などの消化器官や消化液を使って、体の中で少しずつ分解されていくのですが、甘酒の場合は、甘酒を作る段階で麹菌が細かく分解してくれます。
でんぷん→ブドウ糖やオリゴ糖に
たんぱく質→アミノ酸やビタミンに
甘酒を飲む前に、すでに栄養素は分解されているので、体に負担をかけることなく、エネルギーを確保できます。



消化活動って、実はめちゃくちゃエネルギーがいるんです…。
ヒトの体は獲得したエネルギーを使って消化・吸収を繰り返していますが、ストレスや疲労がたまっていたり、体が冷えていたり、十分なエネルギーを得ることができない状況にいると、その分、消化のスピードが遅くなってしまいます。
さらに、消化と吸収にエネルギーを使いすぎると、免疫機能が働きにくくなったり、新陳代謝が滞るため、病気や老化が進む原因になります。
・細胞の新陳代謝が上手くいかず、老化する
・間違った細胞分裂が進み、がんなどの病気にかかりやすくなる
・ウイルスや細菌の影響を受けやすくなり、感染症にかかりやすくなるなど



わーたいへん!
そんな時、甘酒を飲めば、不足しがちなビタミンやミネラルを吸収しやすい形でかんたんに摂取できます。
特に甘酒にはストレスがかると失いがちなビタミンB群が多く含まれているので、心が疲れたり、イライラしている人にもおすすめです。



明らかに顔が疲れている人に甘酒をおすすめすると、顔色がすごくよくなってうれしくなります。



甘酒が体質に合うなら、おいしくて、調子よくて最高!
免疫力を高める酪酸菌が増えるから
甘酒を継続的に飲むと、免疫力を高めます。
そのメカニズムは以下のとおり。
オリゴ糖・食物繊維が含まれた甘酒を食べる
↓
腸内にいる酪酸菌が活性化して、酪酸を作る
↓
善玉菌が暮らしやすい腸内環境ができる
↓
風邪の予防ができる
体内の免疫細胞の約70%は、腸に集中しています。
この約70%の免疫細胞を活性化させるには、腸内環境を整えて、酪酸をはじめとする短鎖脂肪酸を作ることが重要です。
短鎖脂肪酸
=腸内細菌が作る、酪酸、プロピオン酸、酢酸などの有機酸のこと
短鎖脂肪酸の中でも特に酪酸が、免疫細胞の活性化に役立つことがわかってきています。
2013年に独立行政法人理化学研究所などの研究チームが発表した内容(※1)によると、食物繊維が多い食事をとると、酪酸を作る腸内細菌が増え、免疫細胞を活性化し、大腸炎などの病気を防ぐことがわかりました。
食物繊維が多い食事を摂ると酪酸が増加
引用:(※1)腸内細菌が作る酪酸が制御性T細胞への分化誘導のカギ(独立行政法人理化学研究所など)
酪酸が制御性T細胞への分化誘導に重要なFoxp3遺伝子の発現を高める
酪酸により分化誘導された制御性T細胞が大腸炎を抑制
甘酒には食物繊維やオリゴ糖など、腸内細菌の中でも酪酸菌が好きなエサがたくさん含まれています。
これが結果的に免疫細胞を安定させ、風邪を予防してくれます。
食物繊維やオリゴ糖ばかりが、腸内細菌のエサとして取り上げられますが、実は他にも腸内細菌のエサになりやすい成分はたくさんあります。
例えば、酒粕甘酒に多く含まれる、難消化性タンパク質の「レジスタントプロテイン」。
レジスタントプロテインも酪酸菌を増やして、免疫力を上げることが期待される成分のひとつです。
レジスタントプロテイン
=難消化性のタンパク質の一種
=コレステロールを減らしたり、便秘や肥満の改善効果も注目されている
2022年に金沢工業大学で行われた研究(※2)では、レジスタントプロテインが多く含まれた甘酒を1か月間飲むだけで、酪酸を作る腸内細菌の占有率が増え、免疫力が高まることがわかりました。
レジスタントプロテインが含まれた甘酒を食べる
↓
腸内にいる酪酸菌が活性化して、酪酸を作る
↓
善玉菌が暮らしやすい腸内環境ができる
↓
風邪の予防ができる



レジスタントプロテインは米麹甘酒よりも酒粕甘酒に多く含まれているんだって。飲む点滴=米麹甘酒のイメージが強いけど、酒粕甘酒も腸内環境を整えてくれる栄養がたっぷり!



甘酒の種類は、目的別に選ぼう!風邪予防なら米麹甘酒を、ダイエットなら酒粕甘酒がおすすめです。
睡眠効率を上げ、基礎体力の低下を防ぐから
甘酒は睡眠効率を上げ、基礎体力の低下を防ぎます。
そもそもヒトはよく眠れない状態が続くと風邪を引きやすくなるもの。
2009年にアメリカで行われた研究(※3)によると、睡眠効率が悪い人は5.5倍も風邪を引く可能性が高いことがわかっています。
睡眠時間が7時間未満の参加者は、8時間以上の参加者よりも風邪を発症する可能性が2.94倍高い
睡眠効率が92%未満の参加者は、睡眠効率が98%以上の参加者よりも5.50倍風邪をひく可能性が高い
引用:(※3)Sleep habits and susceptibility to the common cold



5.5倍は結構すごいぞ。ぐっすり寝れない人は注意が必要ですね。
睡眠の質が悪い人は、甘酒に含まれる「清酒酵母」を摂取することで、眠りの質が良くなる(=熟睡しやすくなる)という報告(※4)もあります。
清酒酵母
=清酒醸造に用いられる酵母
=日本酒や酒粕だけでなく、醤油や味噌などの発酵食品にも含まれる
さらに、酒麹甘酒には、睡眠の質を改善してくれる「睡眠ホルモン」を作るときに役立つ栄養素を豊富に含んでいます。



最近「ぐっすりと眠れてないな〜」という方は、酒麹甘酒を飲んでみるのもいいかも?
風邪予防に効く!甘酒ちょい足しレシピ


風邪予防するために甘酒にちょい足しするなら、こんなアレンジレシピもおすすめです。
一つずつ見ていきましょう。
しょうが甘酒で体を温める
風邪予防するために甘酒にちょい足しするなら、「しょうが」がおすすめです。
しょうがの辛味成分「ジンゲロール」には、毛細血管を開く作用があり、しょうがと甘酒を一緒に飲めば、血管が拡張して、血流が良くなり、老廃物を外に出してくれる働きがあります。



辛味成分「ジンゲロール」は、風邪の引き始めに飲むと良いと言われる漢方「葛根湯」にも入っている成分です。
しょうが甘酒を作るときは、無農薬のしょうがを使い、皮ごとすっていれるのがおすすめです。
ちょっと風邪を引きそう…のどもちょっと痛い…と言う時に、生姜のすりおろしを追加した甘酒を飲めば、手足の末端まで温まるような気がしますよ。



岩下の新生姜と甘酒のコラボなんてあるんだ!!
トマト甘酒でGABAを摂取する
風邪予防するために甘酒にちょい足しするなら、「トマト」もおすすめです。
トマトには、リコピンという抗酸化作用のある成分や、GABAというストレスを軽減させる癒し成分が豊富に含まれています。
リコピン
=カロテノイドの一種。赤色の天然色素。
=強力な抗酸化作用を持ち、、血流を改善する効果がある
GABA
=アミノ酸の一種。
=ストレスを軽減させる効果がある
=興奮状態を抑え、睡眠に入りやすい環境を整える
甘酒と合わせて飲むと、睡眠の質が良くなったり、ストレスが緩和される効果が期待できます。
ストレスや睡眠不足は、基礎体力の低下や免疫力の低下を招くと言われる要因のひとつ。
トマト甘酒なら、風邪のリスクを減らす基盤を作ることができるのです。



トマトジュースに甘酒を入れるとめちゃくちゃおいしい!甘酒が甘ったるくてニガテという方は、ぜひトマトの酸味と合わせてみて。
いちご甘酒でビタミンCを摂取する
風邪予防するために甘酒にちょい足しするなら、「いちご」もおすすめです。
甘酒は栄養の宝庫ですが、唯一不足している栄養素が「ビタミンC」。
そんなビタミンCを補ってくれるのが、大人気のフルーツ「いちご」というわけ。
もちろん、「いちご」以外にもビタミンCが多いフルーツはたくさんあるので、好きなフルーツや野菜を探してみるのもおすすめです。
【ビタミンCが多い果物】
キウイ
マンゴー
柿
レモン
いちご
トマト



わたしはやっぱりいちごか、キウイ、トマトが好きだなぁ…。甘酒が甘いので酸味が強めのフルーツとよく合います。キウイは食物繊維もたっぷりなので、さらに腸内環境改善効果が期待できます。
ビタミンCを追加する時に気を付けるのは、追加するタイミングです。
ビタミンCは加熱すると壊れやすいので、甘酒が完成して冷やしたあとにトッピングしましょう。ビタミンCが含まれたものをトッピングするのがおすすめです。
甘酒を飲む時間はいつがよい?


甘酒を飲む時間は、自分が毎日無理なく飲める時間をチョイスするのがおすすめです。
タイミング別にメリットを見ていきましょう。
甘酒を朝に飲むメリット
朝甘酒を飲む最大のメリットは、ぶどう糖で脳と体がシャキッと目覚めることです。
甘酒を飲むと、ぶどう糖のエネルギーがチャージされ、体が目覚めます。
体温が上がり、代謝が良くなるスイッチになります。



朝から脳みそをフル回転させたい人はぜひ!!
甘酒を昼に飲むメリット
昼間に甘酒を飲む最大のメリットは、仕事や勉強、家事などのやるべきことを進める集中力がキープしやすくなることです。
どうも頭がさえないなと思ったら、脳を活性化させるために甘酒をおちょこに1杯飲むのもおすすめです。
甘酒を夜に飲むメリット
夜に甘酒を飲む最大のメリットは、疲労回復効果が期待できることです。
甘酒に含まれるGABAの効果もあって、ストレスの緩和やリラックス効果も期待できます。



ホットミルクと甘酒を1:1で割って飲むと、なんかほっこりするんですよね…笑
甘酒は風邪を引いた後に飲むのも効果的
甘酒は風邪の予防によい成分がたくさん含まれていますが、そもそも栄養バランスがよいので、風邪をひいてしまってからもおすすめできる飲み物です。
特に風邪をひいているとのどが痛くて食欲もわかず、固形物が食べられない時があるかと思いますが、そんな時は甘酒の出番です。
固形物を食べる元気はないけど、ちゃんと栄養バランスがいい食事がしたい…と思ったら、まずは甘酒を飲んでみるのもよい方法かもしれません。



甘酒は、大昔から庶民の健康を支えてきたって言われている魅惑の飲み物なのよ…!
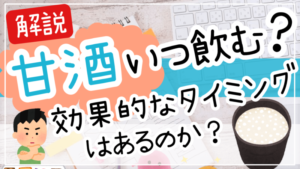
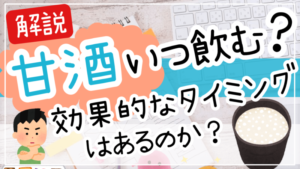
甘酒とは?


甘酒は、日本の伝統的な甘味飲料の一種で、昔から庶民の栄養ドリンクとして親しまれてきました。
江戸時代の日本では、庶民は「甘酒」、お金持ちは「うなぎ」でエネルギー源や代謝によいビタミンB群を摂取して、夏バテを防いでいたのだそう。



今でいう、オロナミンCとか、リポビタンDとかと似た扱いだったのかも?!笑
甘酒の基本成分
➀ブドウ糖:飲む点滴と言われるように点滴にも含まれる活動のエネルギーとなる成分
➁オリゴ糖:腸内細菌のエサになる糖で、善玉菌の活動を活発にする
➂ビタミンB群:糖質や脂質の代謝を助け、体調不良や肌荒れを防ぐ
➃食物繊維:腸内細菌のエサになる繊維で、善玉菌の活動を活発にする



糖が多いので、飲みすぎにはくれぐれも注意してね。
甘酒の種類と効果効能
甘酒には2つの種類があります。
米麹甘酒=米+米麹+水
酒粕甘酒=酒粕+砂糖+水
2つの違いを見てみましょう。
風邪予防におすすめ!「米麹甘酒」の効果効能
風邪予防、便秘改善など毎日の体メンテナンスにおすすめなのは、米麹甘酒です。
「食物繊維」と「オリゴ糖」が豊富に含まれているため、腸内の善玉菌を増やし、排便をスムーズにする効果があります。
さらに風邪を予防し、肌や髪を丈夫に保つ栄養素である、ビタミンB類、ブドウ糖、オリゴ糖、アミノ酸が含まれているのも注目です。
ビタミンB群は、髪の毛の成分であるケラチンの生成を促してくれて、また頭皮の血行をよくし健康な髪質へと導いてくれます。
ダイエットにおすすめ!「酒粕甘酒」の効果効能
ダイエット中の方におすすめなのは、酒粕甘酒です。
酒麹甘酒には「レジスタントプロテイン」という成分が含まれていて、これが肥満の元になる脂質を老廃物とともに体外へ排出してくれる効果があります。
また酒麹甘酒にも多くのアミノ酸や酵素が含まれていて、これらが摂取した食べ物の消化吸収を効率よくしてくれる働きがあります。
このことが、体の代謝アップにもつながり、太りにくい体質にも変わっていきます。
さらに酒麹甘酒は、コラーゲンの減少を抑える働きも注目されています。
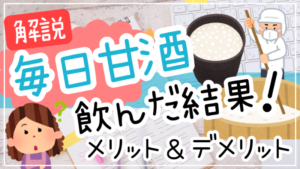
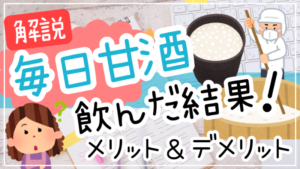
まとめ:風邪予防に甘酒が良い理由3選!体調不良時の飲み方・アレンジ法


甘酒が風邪予防になる理由は、主に以下の3つです。
体調が良くないなと思ったら、栄養補給のためにまずは甘酒でバランスをとるという人も増えています。
その際は、こんなアレンジもおすすめです。
参考にしてみてね。
発酵を体系的に勉強したくなったら…
発酵ライフ推進協会オンライン校へ
\仕事に繋がる無料サポートもたくさん(*´ω`*)/
参考文献
(※1)腸内細菌が作る酪酸が制御性T細胞への分化誘導のカギ(独立行政法人理化学研究所など)
https://www.riken.jp/press/2013/20131114_1/
(※2)市販の甘酒と比較し約6倍のレジスタントプロテインを含有(金沢工業大学)
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitnews/2022/0630_a-amasake.html
(※3)Sleep habits and susceptibility to the common cold
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19139325/
(※4)酒粕などに含まれる清酒酵母に”睡眠の質”を高める効果 – ライオンが確認
https://news.mynavi.jp/article/20140513-a238/