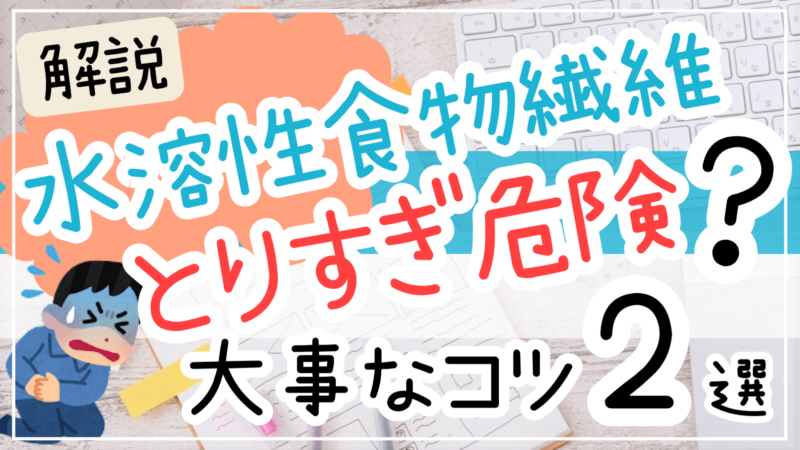今回はこんな疑問にお答えします。
・水溶性食物繊維をとりすぎると、栄養素が十分に吸収されなかったり、下痢になる可能性も!
・水溶性食物繊維は不溶性食物繊維と比べると不足しやすく、過剰摂取のケースは少ない。
・水溶性食物繊維の一日の推奨量は、男性7g、女性6g程度なので、意識してとるのがおすすめ。
ヒトが生きていく上で大事な「7大栄養素」と言えば、「タンパク質」「糖質」「脂質」「ビタミン」「ミネラル」「フィトケミカル」…そして今回のテーマの「食物繊維」です。
食物繊維は腸活に大事な栄養素としても有名ですが、とりすぎても体に悪影響があるということをご存じでしょうか?
そこで今回は、食物繊維はとりすぎるとどうなるのかを徹底解説!
一日の推奨量ととり方のコツもおさらいします。



結論!水溶性食物繊維をとりすぎるとどうなる?
水溶性食物繊維をとりすぎると、水溶性食物繊維の性質上、体に必要な栄養素の吸収を抑えてしまい、栄養素が効率的に吸収されない可能性が高くなります。
また、体質によっては腸を刺激して下痢や軟便を招くケースも考えられます。
水溶性食物繊維の種類によっては、腹痛や下痢、下痢によるミネラル欠乏症などの報告があるものもあり、注意が必要です。
詳しく見ていきましょう。
食物繊維とは?
食物繊維はヒトが生きていく上で大事な栄養素のひとつです。



たしかに、7大栄養素のうち、食物繊維以外の6つはすべて消化・吸収されることが前提の栄養素なのに、食物繊維だけは消化・吸収されません。
胃や小腸では消化・吸収されず、大腸まで届く…という点が食物繊維のいちばん大きな特徴です。
しかし、食物繊維が5大栄養素に入れてもらえず、「あまり重要ではない」と思われていたのは昔のはなし。



今は、むしろ消化吸収されずに、大腸まで届く唯一の栄養素として、とても重要な役割をしていることがわかってきています。
大腸まで届いた食物繊維が何をするのか。それは、食物繊維の種類によって異なります。
食物繊維の種類
食物繊維には水に溶ける「水溶性食物繊維」と水に溶けない「不溶性食物繊維」の2種類があります。
不溶性食物繊維=水に溶けない



食物繊維の基本的な働き
食物繊維は体内で消化されないので、糖質やタンパク質などのように直接栄養を与える働きはありません。
しかし、直接栄養を与えなくても、「胃腸の機能を安定させ、老廃物を体の外に出し、腸内環境を整える」という大事な役割があります。
=胃腸の機能を安定させ、老廃物を体の外に出し、腸内環境を整えること
食物繊維の種類別の働き
水に溶ける水溶性食物繊維は、腸内の善玉菌のエサになり、腸内環境を整えてくれます。
一方、水に溶けない不溶性食物繊維は腸内の老廃物のカサを増やして、腸に刺激を与え、腸のぜん動運動を活性化します。
水溶性食物繊維=腸内の善玉菌のエサになり、腸内環境を整える
・脂質を吸着して体外に排出し、血液中のコレステロール値を低下させる
・ナトリウムを排出して高血圧を予防する
不溶性食物繊維=腸に刺激を与え、腸のぜん動運動を活性化する
どちらも腸内環境を整えるためには重要です。
水溶性食物繊維と不溶性食物繊維は、1:2を目安に食べることが推奨されています。
水溶性食物繊維のほうが含まれている食べ物が少ないため、不足しやすいと言われているからです。
=果物類・野菜類(ペクチン)
=野菜類・いも類(イヌリン)
=海藻類(アルギン酸)
=穀物類(β-グルカン)
=こんにゃく(グルコマンナン)など
=野菜類などの植物性食品(セルロース、ヘミセルロースなど)
=きのこ類(キチン)など



\今なら2000円OFFでお得 (*´ω`*)/
一日の推奨量はどのくらい?(とりすぎの基準)
厚生労働省が発表している「日本人の食事摂取基準(2020 年版)」によると、食物繊維の年代別、性別ごとの摂取目標量は以下の通りです。
| 年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 0 ~ 5か月 | ─ | ─ |
| 6 ~11か月 | ─ | ─ |
| 1 ~ 2 (歳) | ─ | ─ |
| 3 ~ 5 (歳) | 8 以上 | 8 以上 |
| 6 ~ 7 (歳) | 10 以上 | 10 以上 |
| 8 ~ 9 (歳) | 11 以上 | 11 以上 |
| 10~11(歳) | 13 以上 | 13 以上 |
| 12~14(歳) | 17 以上 | 17 以上 |
| 15~17(歳) | 19 以上 | 18 以上 |
| 18~29(歳) | 21 以上 | 18 以上 |
| 30~49(歳) | 21 以上 | 18 以上 |
| 50~64(歳) | 21 以上 | 18 以上 |
| 65~74(歳) | 20 以上 | 17 以上 |
| 75 以上(歳) | 20 以上 | 17 以上 |
| 妊 婦 | ─ | 18 以上 |
| 授乳婦 | ─ | 18 以上 |
引用:日本人の食事摂取基準(2020 年版)
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf



厚生労働省が運用する生活習慣病予防のための健康情報サイト「Eヘルスネット」によると、日本人の平均食物繊維摂取量は年々減少しています。
最近の報告によると、1日の食物繊維の平均摂取量は14g程度/日とのことなので、男女ともに推奨量に足りていません。
昔ながらの和食は穀類やいも類・豆類が多いので、自然と食物繊維の量が増えがちでした。
摂取する食物繊維量が減っている原因のひとつに食の欧米化も関係していると言われています。



水溶性食物繊維、とりすぎるとどうなる?
食物繊維は、普通の食事からとる分にはとりすぎの心配はありません。



でも、最近は食事から十分な食物繊維をとるのが難しいと感じ、サプリメントなどで追加摂取する人が多いのが気になります。
サプリメントの場合は、自然な方法では絶対にとることができない量がとれてしまう可能性があるので、悪影響を及ぼす可能性はゼロではありません。
水溶性食物繊維のとりすぎによるデメリットは以下のとおりです。
とりすぎデメリット➁ 下痢や軟便になる
一つずつ見ていきましょう。
とりすぎデメリット➀ 栄養素が十分に吸収されない
水溶性食物繊維は、栄養を小腸で吸収するスピードを緩やかにします。
そのため、血糖値やコレステロール値があがりにくくなり、肥満や糖尿病などの生活習慣病を予防する効果があります。
しかし、とりすぎると他の有効な成分であるビタミンやミネラルなど、体が必要としている栄養素の吸収までもを抑えてしまい、食事から十分な栄養素が吸収できなくなる可能性があります。
ただしすべての水溶性食物繊維が栄養素の吸収を抑えるというわけではありません。
水溶性食物繊維の中でも粘度が高いペクチンやアルギン酸は、その傾向が強いと言われています。
またペクチンやサイリウムなどを粉末で大量に摂取すると、水分の多くが水溶性食物繊維に吸い取られてしまい、腸内が水分不足に陥る可能性があります。
動物実験の段階では、腸内の水分不足がきっかけとなり、胃や小腸の細胞にキズをつけてしまうケースも報告されています。



とりすぎデメリット➁ 下痢や軟便になる
水溶性食物繊維は、腸を刺激して下痢や軟便を招くケースが考えられます。
食品に含まれている食物繊維のみでとりすぎになることはほぼありません。しかし、食物繊維のサプリメントを大量に飲むなど、普通の摂取方法以外で飲む場合は注意が必要です。



=生理学的な機能に影響を与える保健効能成分(関与成分)を含む食品のこと
水溶性食物繊維の種類によるデメリットも確認してみましょう。
種類別デメリット➁ 機能性表示食品「イヌリン」の場合
種類別デメリット➀ 特定保健用食品「難消化性デキストリン」の場合
アメリカのFDA(食品医薬品局)は、難消化性デキストリンは安全性が高く、1日の摂取量の条件を設ける必要はないと報告しています。



難消化性デキストリンは、水溶性食物繊維の中では粘度が低い「低分子水溶性食物繊維」に分類されるため、変化がゆるやかで、人によっては効果を感じないこともあるようです。



種類別デメリット➁ 機能性表示食品「イヌリン」の場合
イヌリンは菊芋などの植物に多く含まれている水溶性食物繊維で、その安全性は高いと言われています。
しかし、サプリメントを過剰摂取すると、腹痛や下痢、下痢によるミネラル欠乏症を引き起こす恐れがあるため注意が必要です。



健康を害するほど食べ過ぎるのはNGです。また、合わないならムリして飲み続けることはやめましょう。
不溶性食物繊維、とりすぎるとどうなる?
水溶性食物繊維と比べて、不溶性食物繊維はとてもとりやすい栄養素です。
食物繊維をとろうとすると、そのほとんどの食品に不溶性食物繊維がたくさん含まれているからです。(水溶性食物繊維はあまり含まれていないものも多い)
もち麦・玄米などの穀類
キャベツなどの腸によいイメージがある野菜類
まいたけ・えのきなどのきのこ類など
不溶性食物繊維のとりすぎデメリットは以下のとおりです。
詳しく見てみましょう。
とりすぎデメリット➂ 便秘が悪化する
不溶性食物繊維をとりすぎると、消化できない成分が一度にたくさん腸に溜まり、腸のぜん動運動がしにくくなります。
便が硬くなって詰まってしまい、その詰まった便から腐敗ガスが大量に発生し、お腹がはってしまうケースも少なくありません。
その結果、便秘を悪化させることも多くなります。
食物繊維のとり方のコツ
食物繊維はとらなくても、とりすぎてもよくありません。健康や美容のためには、とり方にコツがあります。
コツ➁ 十分にとれたら「水溶性:不溶性=1:2」を意識する
一つずつ見ていきましょう。
コツ➀ まずは推奨量の男性21g、女性18gを意識する
食物繊維はとりすぎよりも不足のほうが、腸内環境に与えるリスクが高いです。
・便秘による腸内環境の悪化
・腸内環境の悪化による生活習慣病リスクの増加(肥満・糖尿病など)
・腸内環境の悪化による大腸がんリスクの増加
・腸内環境の悪化によるうつ病リスクの増加など
まずは、食生活を見直し、食物繊維の1日の推奨量がムリなくとれるメニューを探しましょう。
どうしても食事から食物繊維をとるのが難しい場合のみ、サプリメントや健康食品に頼ることも検討したいですが、自分の体に合わない食物繊維をとり続けるのはおすすめしません。
体の様子を観察しながら、無理のない範囲で活用しましょう。
コツ➁ 十分にとれたら「水溶性:不溶性=1:2」を意識する
食事から十分な食物繊維がとれるようになったら、次は食物繊維のバランスも意識しましょう。
水溶性食物繊維が1に対し、不溶性食物繊維が2の割合がいちばんよいバランスだと言われています。
厚生労働省が発表した平成30年国民健康・栄養調査報告によると、現在は水溶性食物繊維が1に対し、不溶性食物繊維が4のバランスでとっている方が多いようです。
この割合が続くと、腸のぜん動運動が弱いタイプの方は、ますます便秘がひどくなる可能性もあり得ます。
ひとつひとつの食品の水溶性食物繊維と不溶性食物繊維のバランスを見た時に、理想に近い食品として注目されているのは、以下の食品です。
| 総量 | 不溶性食物繊維 | 水溶性食物繊維 | バランス比 | |
|---|---|---|---|---|
| ごぼう | 5.7g | 3.4g | 2.3g | 1.5:1 |
| オートミール | 9.4g | 6.2g | 3.2g | 1.9:1 |
| アボカド | 5.6g | 3.9g | 1.7g | 2.3:1 |
| オクラ | 5g | 3.6g | 1.4g | 2.6:1 |
| りんご | 1.9g | 1.4g | 0.5g | 2.8:1 |
| キウイフルーツ | 2.6g | 2g | 0.6g | 3.3:1 |
参考:日本食品標準成分表2020年版(八訂)



まとめ:水溶性食物繊維、とりすぎるとどうなる?
水溶性食物繊維のとりすぎによるデメリットは以下のとおりです。
とりすぎデメリット➁ 下痢や軟便になる
水溶性食物繊維は、栄養を小腸で吸収するスピードを緩やかにして、血糖値やコレステロール値をあげないというメリットがある一方、とりすぎると他の有効な成分であるビタミンやミネラルなど、体が必要としている栄養素の吸収までもを抑えてしまい、食事から十分な栄養素が吸収できなくなる可能性があります。
また、サプリメントや粉末などで粘度が高いペクチンやアルギン酸をとると、水分の多くが水溶性食物繊維に吸い取られてしまい、腸内が水分不足に陥ったり、胃や小腸の細胞にキズをつけてしまうこともあります。
また、不溶性食物繊維をとりすぎると、消化できない成分が一度にたくさん腸に溜まり、腸のぜん動運動がしにくくなります。
便が硬くなって詰まってしまい、その詰まった便から腐敗ガスが大量に発生し、お腹がはってしまうケースも少なくありません。
その結果、便秘を悪化させることも多くなります。
食物繊維はとらなくても、とりすぎてもよくありません。健康や美容のためには、とり方にコツがあります。
コツ➁ 十分にとれたら「水溶性:不溶性=1:2」を意識する
気軽にいろんな種類の食物繊維をとりたい…とお思いの方は、食物繊維はもちろん、82種類の薬草成分を3年半発酵熟成させたエキスが入ったオーガニックハーブティーもおすすめです。
実際に腸体温が1℃上がって、乳酸菌とビフィズス菌がともに1.8倍に増えたと言うデータも!
冷え症や便秘や肌荒れが気になる方、最近痩せにくくなったなぁ…とお思いの方は参考にしてみてね。
\今なら2000円OFFでお得 (*´ω`*)/
参考文献
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jim1987/8/2/8_2_125/_pdf?_ga=2.169359649.1638810471.1656589372-1849347510.1656589372