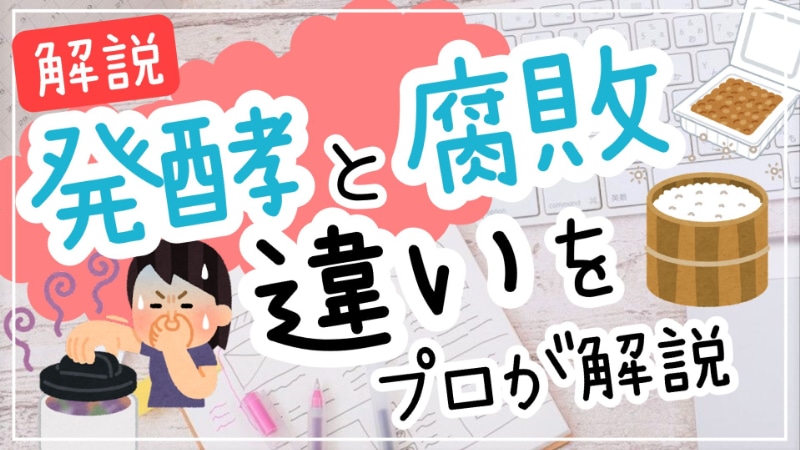【この記事で解決できるお悩み】
・発酵と腐敗の違いってなに?
・発酵食品って腐ってるの?わかりやすくおしえて
・NHKで放送中の「チコちゃんに叱られる!」で語られた発酵と腐敗の違いも知りたい!



この記事では、こんなお悩みを解決します!
発酵食品ブームの到来によって、「発酵」という言葉が一般的によく使われるようになりました。
そして、「発酵」と同時に使われるようになったのが、「腐敗」とか「腐ってる」という言葉。
「納豆は腐っているから、これ以上腐らない」っておっしゃる人がいますが、本当に「納豆は腐っている」んでしょうか?
そこで今回は、似ているようで似ていない「発酵」と「腐敗」の違いを徹底解説!
NHKで放送中の「チコちゃんに叱られる!」で放送された、チコちゃん流の解説もご紹介します。
発酵を体系的に勉強したくなったら…
発酵ライフ推進協会オンライン校へ
\仕事に繋がる無料サポートもたくさん(*´ω`*)/


この記事を書いた人:
腸活研究家 長谷川ろみ
発酵食品にハマり、ダイエットなしで12㎏減。痩せたことをきっかけに腸を愛でる生活に目覚める。重度の便秘から解放され、腸活研究家として活動開始。今では発酵ライフ推進協会通信校校長を務め、昔の自分と同じ悩みを持つ方に向けて腸や菌のおもしろさを発信中。詳しくはこちら
発酵と腐敗の違いをわかりやすく解説


発酵と腐敗の違いは、実はとても単純です。
わかりやすく言うならば、最後に残る物質が「有益」か「有害」か。
発酵:微生物がヒトに「有益」な物質をつくること
腐敗:微生物がヒトに「有害」な物質をつくること
では、なぜややこしい気がするかというと、「発酵」と「腐敗」がヒトによるヒトのための分け方だから。
微生物からみると、「発酵」と「腐敗」は全く同じもの(=メカニズム)なのが、複雑に見える要因です。
微生物からみると、発酵と腐敗は同じもの
発酵の結果、できあがったものが「有益」か「有害」かは、あくまでヒトが勝手に決めたことです。
有益(=うれしい)
・おいしい
・うま味が多い
・いいにおいがする
・ビタミンやミネラルが多い
・有機酸が多く、腸内環境を整える など
有害(=つらい)
・まずい
・苦い
・くさい
・吐き気がする
・おなかが痛くなる
・下痢になる など



どっちもヒトの五感に関わることで、うれしいとかつらいと感じるのはヒトですよね。
でも、実際に発酵活動をしている微生物からみたら、この2つは全く同じこと。
微生物にとっての発酵と腐敗は、人間にとっての呼吸と同じ。ただの生命活動なのです。
| 生命活動 | |
|---|---|
| 微生物 | 発酵・腐敗 |
| 植物 | 光合成 |
| 動物(人) | 呼吸 |
ヒトも微生物と同じように、空気中に含まれる窒素(約80%)、酸素(約20%)、二酸化炭素(約0.03%)を吸って、窒素(約80%)、酸素(約16%)、二酸化炭素(約4%)、その他体内で発生したガス(約1%)を出しています。
呼気に含まれる成分のうち80%近くは窒素で、残りの2割が酸素(16%)、二酸化炭素(4%)であり、この他に、体内で発生した微量のガスが1%ほど含まれている。
引用:科学と技術|政府広報オンライン



ヒトも呼吸によって二酸化炭素を増やしてます。でも、わざわざ有益(=発酵)と有害(=腐敗)の呼び方を分けることはないですよね。微生物からしたら余計なお世話よね…笑
ヒトからみると、発酵は有益で腐敗は有害
微生物の発酵と腐敗は、ヒトからみるとちゃんと分けておかないと危険です。
発酵かと思って食べたら、腐敗していたとなると、さあ大変。
お腹は痛くなるわ、しばらく寝込む可能性もありますし、病気で生死をさまよう危険性もあります。
だから私たちは、これは発酵、これは腐敗と明確に分けて意識する必要があるのです。
| 発酵の例:味噌づくり | 腐敗の例:ヒスタミン食中毒 |
|---|---|
| コウジカビが米のデンプンをブドウ糖に変化させる コウジカビが豆のタンパク質をアミノ酸い変化させる 乳酸菌がブドウ糖をエサに乳酸を作る 酵母菌がブドウ糖をエサにアルコールや臭気成分を作る | ヒスタミン産生菌が魚介類に含まれるヒスチジン(アミノ酸の一種)をヒスタミンに変化させる |
発酵と腐敗の違いは文化によって変わる
発酵学者の小泉武夫先生が、以前このような発言をされました。
発酵か腐敗かを分けるのは科学ではなく、文化である。
微生物の活動がヒトにとって有益かどうかを決める基準は、食文化や食習慣によっても異なります。
例えば、納豆という食べ物を知らない他国の人に納豆を食べさせたら、腐敗していると感じる可能性は多いにあります。
逆に日本人がアメリカ・アラスカ州のエスキモー民族がつくるアザラシの内臓の中で作る海鳥の漬物「キビヤック」を口にしたら、腐っていると思うでしょう。
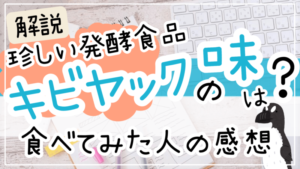
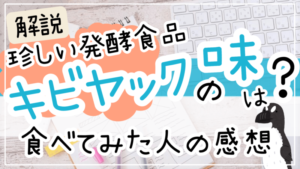
16世紀に来日したイエズス会の宣教師ルイス・フロイスが著書「フロイスの日本覚書」の中で、日本人が食べる塩辛への驚きを文章にしています。
我々においては、魚の腐敗した臓物は嫌悪すべきものとされる。日本人はそれを肴として用い、非常に喜ぶ
引用:フロイスの日本覚書 : 日本とヨーロッパの風習の違い(松田毅一, E.ヨリッセン 著)



確かに最初に塩辛を食べた人は、すごいなと日本人のわたしも思います。笑 結局、文化次第で発酵と腐敗の定義は変わってしまう可能性があるということです。
発酵と腐敗の違いのチコちゃんの解説


2020年2月にNHKで放送された「チコちゃんに叱られる!」の番組内の「発酵食品の謎」のコーナーでは、チコちゃんが発酵と腐敗の違いについて、こう答えました。
整理してご紹介しましょう。
チコちゃん流!お腹が痛くなると腐敗
チコちゃんの発酵と腐敗の違いは、以下のとおり。
お腹が痛くなるかならないか



なるほど!たしかにそうかもしれない!!笑 お腹が丈夫な人は、だいぶ腐敗の範囲が狭まるけども…。
発酵と腐敗の違いのポイントは、「お腹」の変化
ヒトのお腹が下ったり(下痢)、痛くなる(腹痛)メカニズムは以下のとおり。
【下痢になるメカニズム】
毒素を出す菌が付いている食べ物を食べる
↓
毒素を出す菌が胃や腸内でも毒素をたくさん出す
↓
毒素を感知した腸が大量の水分を分泌し、毒素を体外に出そうとする(下痢)
【腹痛になるメカニズム】
毒素を感知した腸が大量の水分を分泌し、毒素を体外に出そうとする(下痢)
↓
腸の毒素を体外に出そうとする働きが痛みとして脳に伝わる(腹痛)



腹痛や下痢になるかどうかは、普段の食習慣にもよります。地元の方が普通に食べている食料を旅行者が食べると、強烈な腹痛や下痢に繋がることもあります。
例えば、中国産「ヘドロアサリ」のケースもとても興味深い例です。
夕方、ホテルへ戻ると、断続的な吐き気と腹痛に襲われた。厚生労働省が発表している「輸入食品違反事例」によれば、摘発されるアサリの「不適格内容」は「大腸菌群」が散見される。ただ、昼に食べた「酒蒸し」は、火を通して菌が死んでいるはずではないのか。加熱処理が不十分だったか、それとも腐敗していたのか。理由は不明だったものの、翌朝まで下痢でトイレから離れられなくなった。
引用:食べて一晩中トイレから出られなかった中国産「ヘドロアサリ」の恐怖|文春オンライン



うわぁ…ちょっとさすがにコワい…。いくら発酵食品好きでもちょっと遠慮したいです…。
発酵と熟成の違い





そういえば、熟成肉ってよく聞くけど、これは発酵したお肉ってこと?



いやいや、近いけど違うの。熟成は微生物の働きは関係ないよ。
熟成は、微生物の働きとは関係なく、酵素と環境によってお肉などの食べ物が変化することを言います。
熟成
=自らの酵素と環境(時間・温度・湿度)のコントロールによって、タンパク質などが変化すること



例えば熟成肉!肉があらかじめ持っている酵素によって、肉のタンパク質が分解され、うま味が増えたり、柔らかくなった肉のことを熟成肉と呼ぶよ。美味しくするためには、温度や湿度、時間などの環境管理も重要なの。
| 変化の原因 | 有効性 | |
|---|---|---|
| 腐敗 | 微生物の働き | 有害 |
| 発酵 | 微生物の働き | 有益 |
| 熟成 | 酵素 | 有益 |
熟成の3つの種類
熟成といっても、その環境の作り方によっていろんな方法があります。
枯らし熟成
=昔からある方法
=肉を骨が付いたまま吊るし、3~4週間寝かす
=表面についたカビをそぎ落として、中だけ食べる
=廃棄率が高く、効率が悪い
ウェットエイジング
=劣化を防ぐための輸送法でうま味はそんなに増えない
=真空状態の貯蔵庫で、1~2週間寝かす
=カビは少なく、廃棄率は低い
ドライエイジング
=新しい方法(アメリカから伝わった技法)
=専用の貯蔵庫の中で湿度と温度の管理をしながら、1週間~数か月寝かす
=アミノ酸がたくさん増え、うま味が増し、食感も柔らかくなる
=表面についたカビをそぎ落として、中だけ食べる
=廃棄率が高く、効率が悪い



近年流行っているうま味が多くなる柔らかい熟成肉は、ドライエイジングの場合が多いよ。
おすすめドライエイジングビーフ!日本一の鹿児島黒牛熟成肉


\ 本格派のドライエイジングビーフが食べたいならコレ(*´▽`*)/
まとめ:発酵と腐敗の違いをプロがわかりやすく解説!
発酵と腐敗の違いは、実はとても単純です。
わかりやすく言うならば、最後に残る物質が「有益」か「有害」か。
発酵:微生物がヒトに「有益」な物質をつくること
腐敗:微生物がヒトに「有害」な物質をつくること
2020年2月にNHKで放送された「チコちゃんに叱られる!」の番組内で語られた発酵と腐敗の違いは、お腹が痛くなるかならないかでした。
どちらも正しいと言えますが、発酵と腐敗の違いは文化によって変わるので正直に言うとあいまいです。
さらに近年流行している熟成肉の「熟成」も混乱しやすいので、微生物の働きとは関係がないことを覚えておきましょう。
| 変化の原因 | 有効性 | |
|---|---|---|
| 腐敗 | 微生物の働き | 有害 |
| 発酵 | 微生物の働き | 有益 |
| 熟成 | 酵素 | 有益 |
参考にしてみてね。
発酵を体系的に勉強したくなったら…
発酵ライフ推進協会オンライン校へ
\仕事に繋がる無料サポートもたくさん(*´ω`*)/