【この記事で解決できるお悩み】
納豆が糸ひかない!コレって腐ってる?
納豆を食べるとシャリシャリする原因は?
もう食べられない腐敗した納豆の見分け方をおしえて!



この記事では、こんなお悩みを解決します!
白いごはんのお供として人気の発酵食品、「納豆」。
スーパーやコンビニでも手軽に買えて、他のタンパク源と比較すると値段も安いので、健康や美容が気になる人に愛され続けています。
しかし、どんどん発酵が進み、形を変えていく発酵食品であるがゆえに、どこまでが食べられて、どこからが腐っているのか、よくわからないという方も多いようです。
そこで今回は、納豆が腐っているサインを徹底解剖!
糸ひかない納豆や、白い粒がついていて食べるとシャリシャリする納豆、くさ~い異臭を放つ納豆が、なぜそうなるのか、そして、そうなった場合に食べられるのか食べられないのかを、ひとつずつ解説します。
発酵を体系的に勉強したくなったら…
発酵ライフ推進協会オンライン校へ
\仕事に繋がる無料サポートもたくさん(*´ω`*)/


この記事を書いた人:
腸活研究家 長谷川ろみ
発酵食品にハマり、ダイエットなしで12㎏減。痩せたことをきっかけに腸を愛でる生活に目覚める。重度の便秘から解放され、腸活研究家として活動開始。今では発酵ライフ推進協会通信校校長を務め、昔の自分と同じ悩みを持つ方に向けて腸や菌のおもしろさを発信中。詳しくはこちら
糸をひかない納豆の原因


糸をひかない納豆は、存在します。
腐っている可能性ももちろんゼロではありません。しかし、必ずしも100%腐っているわけではありません。
特に納豆が製造されてから時間が経ち、保存している途中で発酵が進み過ぎ、味が落ちている時にネバネバした糸がひきにくくなるのもたしかです。
納豆が糸を引かない理由は、以下の3つのパータンに分類できます。
一つずつ見ていきましょう。
納豆菌が弱くなっている
納豆が糸をひかない・ネバネバしない原因の1つ目は、納豆菌が弱くなっているからです。
製造から時間が経ち、保存状態もあまりよくないと、納豆菌は元気がなくなり、発酵活動も弱まります。
納豆の糸の正体は、納豆菌の発酵によってつくられた「γ-ポリグルタミン酸」です。
納豆菌の発酵の働きが弱まると、「γ-ポリグルタミン酸」が少なくなるため、ねばねばした糸をひかなくなります。
納豆菌にもいろいろな種類があるので、もともと糸をひきやすい菌・ひきにくい菌がありますが、どちらにしろ時間がたつと発酵力が弱まり、少しずつネバネバした糸が減っていきます。



「納豆はもともと腐っているんだから、そんなに急いで食べなくても大丈夫」ってよく聞くけど、糸をひかなくなった納豆はうま味も弱くておいしくないんよね…。せっかくなら、納豆だっておいしいうちに食べたい!
さらに、納豆菌にはいろいろな種類がありますが、ごくまれに糸を引きにくい納豆菌が存在します。
納豆学会の説明によると、これは納豆菌の染色体上に寄生している動く遺伝子・IS因子(IS4Bsu1)が原因とのこと。
納豆菌を培養している際、フラフラと自由にしているIS因子が、納豆の糸の成分であるポリグルタミン酸(PGA)の生産を制御するComP遺伝子に入り込むことによって糸を引かなるわけです。
引用:納豆菌の糸引き不安定性|納豆学会



わたしたちヒトに個性があるように、納豆菌にも個性があるってこと!
雑菌が繁殖している
納豆が糸をひかない原因の2つ目は、雑菌が繁殖しているからです。
1つ目の理由の「納豆菌が弱くなっている」にも通ずるのですが、雑菌の勢力が強ければ、納豆菌は元気がなくなりますし、納豆菌が元気であれば雑菌は繁殖しにくくなります。(発酵菌が常に縄張り争いをしてるようなイメージです)
雑菌が入ると、納豆が糸をひかなくなるだけでなく、カビが生えるなどして腐敗が始まるもとになりますので注意が必要です。



これがいちばんコワイパターンです。雑菌が入ったら美味しくないだけじゃなくて、もう食べられません。
もともと糸をひかない納豆である
納豆が糸をひかない原因の3つ目は、もともと糸をひかない納豆だからです。
納豆は大きく分けると、以下の2種類があります。
糸引き納豆:一般的にスーパーなどで買うことができる、ねばねばした糸をひく納豆
塩辛納豆:大豆と小麦と麹菌を一緒に塩水に漬け込んで、熟成させて作る納豆。別名「寺納豆」ともいう。
塩辛納豆は、中国に留学していたお坊さんが仏教とともに伝えた豆鼓(とうち)に由来しています。
豆を使った発酵調味料で、現代も地方のお寺などでは販売され、名物になっています。



お坊さんが運んできた納豆だから、「寺納豆」って呼ばれるようになったんだって。
【有名な塩辛納豆】
浜納豆:静岡県浜松地方の塩辛納豆。徳川家康が好んでいたことで有名。
大徳寺納豆:京都の大徳寺で売られている名物の塩辛納豆。京都には大徳寺納豆を使った京菓子も存在する。
塩から納豆は、乾燥していて硬いのですが、うま味はたっぷり!
水分がないので、糸引き納豆よりもさらに腐りにくい納豆です。



塩辛納豆(寺納豆)は、かなりしょっぱいのでお茶請けやおつまみとして食べます。調味料として使うと、コクや旨味が追加できて美味!
納豆が糸ひかない納豆がおいしくない理由


「そもそも納豆は発酵食品だから、腐っている。もともと腐っているから、腐らない」という人がいます。



でもこの論調には、若干違和感が…
「腐らない」という言葉は、若干あいまいです。
納豆にも賞味期限はあるため、他の食品同様に確実に品質・味は落ちていきます。
賞味期限が書いてあるということは、納豆にも鮮度や旨味が損なわれて、おいしく食べられないタイミングがあるということです。
さらに納豆は「発酵」はしていますが、「腐敗」はしていません。人によっては、この違いがごっちゃになってしまっているケースがあるようです。
納豆にも賞味期限があるから
納豆にも、他の食料品と同じように「賞味期限」があります。
賞味期限とは、おいしく食べられる目安の期限のことです。
賞味期限:おいしく食べられる目安の期限。過ぎると鮮度や旨味が損なわれる
消費期限:食べられる目安の期限。過ぎたら食べないほうが良い
納豆は賞味期限までに食べないとおなかを壊すわけではないですが、糸を引かなくなり、ネバネバもなくなり、ぽてっとしたただの豆になっていて、あまりおいしくありません。



ぜんぜん鮮度がないんだよね…糸を引かない納豆…
糸をひかない=過発酵状態で質が良くないから
「納豆はもともと腐っている」と言われることがありますが、厳密にいえば、これは間違いです。
〇 納豆はもともと発酵している
× 納豆はもともと腐っている(腐敗している)
納豆が発酵食品ですが、腐敗食品ではありません。
しかし、間違える気持ちもわかります。なぜなら、発酵も腐敗も科学的メカニズムは全く同じことだから。
この定義は、人間からみて有用か、有害かで分けられます。
発酵:微生物が行う作用のうち、人間にとって有用なこと
腐敗:微生物が行う作用のうち、人間にとって有害なこと
納豆の発酵:納豆菌が発酵し、栄養を作ってくれること
納豆の腐敗:納豆菌以外の有害菌が腐敗し、栄養がなくなること
糸を引きにくくなり、ネバネバしなくなり、ぽてっとした納豆は、腐敗しているわけではなく、過発酵状態(=発酵しすぎてしまった状態)です。
納豆菌の力が弱くなり、納豆菌が減ってしまうと、外から入ってきた雑菌が繁殖し、納豆が腐敗するケースもゼロではありません。



納豆は納豆菌が繁殖して作ってくれている間は発酵であり、それが長くつづいても過発酵で腐敗にはなりませんが、違う雑菌(有害菌)が入ってきて繁殖しちゃったら腐敗になります。
食べられるが、発酵しすぎておいしくない納豆の特徴


腐敗はしていなくても(雑菌が入っていなくても)、納豆は発酵しすぎると味が落ちます。
食べられるが、発酵しすぎておいしくない納豆の特徴は、以下のとおり。
一つずつ見ていきましょう。
糸をひかなくなる/ネバネバが弱くなる
納豆が発酵しすぎると糸をひかなくなり、ネバネバが弱くなり、味が明らかに落ちます。
納豆のネバネバの正体は、前述した「γ-ポリグルタミン酸」です。



γ-ポリグルタミン酸は、旨味のもと!
納豆はたくさん混ぜたほうがおいしくなりますが、その理由はたくさん混ぜることによって、もともと納豆に含まれる「γ-ポリグルタミン酸」が細かく切れて、うま味成分の「グルタミン酸」に変化するからです。
グルタミン酸
=昆布などに多く含まれるアミノ酸の一種。うま味のもと(おいしさのもと)だと言われている。



納豆が古くなって粘りがなくなると、グルタミン酸も少なくなるので、うま味が減ってしまいます。うま味が少ないとわたしたちは「おいしくない」と感じやすいんですよね。
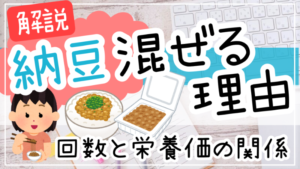
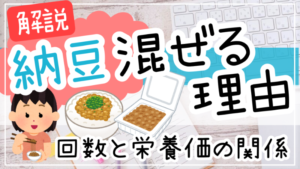
噛むとシャリシャリする
納豆が発酵しすぎると、シャリシャリとした砂を噛んでいるような違和感が生まれることがあります。
これは、過発酵によって豆の表面にできたアミノ酸の結晶「チロシン」です。
チロシン
=非必須アミノ酸の一種
=神経や脳の神経伝達をサポートする



過発酵した納豆の表面に、まれに白い粒が見えることがあるよ。これが、チロシン!
この白い粒「チロシン」は有害なものではありません。
しかし、噛むと砂を噛んでいるような違和感があるので、美味しいとは言えません。



たまにチロシンのことを「白カビ」と間違えている人がいますが、チロシンはただのアミノ酸で、むしろ体に良い成分です。ただな~…おいしくはないんですよ。うん。
腐っているわけではないのですが、この時点で、食べたくないと思う方もたくさんいらっしゃると思います。
苦味がでる
納豆が発酵しすぎると、納豆の旨味や甘みが減り、苦味が出やすくなると言われています。
納豆の苦みのもとは、過発酵によって生まれた「アミノ酸」です。
納豆菌は発酵の過程でたくさんのアミノ酸を作りますが、アミノ酸はそれぞれうま味、酸味、甘味、苦みなどの味を持っています。
九州大学の研究(※1)によると、アミノ酸の種類によって、人が感じる味は大きく異なります。
| うま味 | 酸味 | 甘味 | 苦み |
|---|---|---|---|
| グルタミン酸 | アスパラギン酸 | グリシン、アラニン、トレオニン、セリン、グルタミンなど | トリプトファン、フェニルアラニン、イソロイシン、アルギニン、ロイシン、バリン、システイン、メチオニン、リジン、ヒスチジン、チロシンなど |
甘味を感じるアミノ酸が多ければ、甘味の多い納豆に、苦みを感じるアミノ酸が多ければ、苦みの多い納豆になります。
このアミノ酸の組み合わせが納豆の味を決める要素の1つになっています。



特に私たち人間は「グルタミン酸」が多い納豆をおいしく感じやすいみたい!逆にイソロイシンやバリン、リジンなどが多いと苦く感じるんだって。
2009年の福岡女子短大の研究内容(※2)によると、「グルタミン酸」と「直接還元糖」が多いほど人間は美味しく感じることがわかっています。
しかし賞味期限切れ間近なものでは,わずかに粘度が下がるものの,直接還元糖量および遊離グルタミン酸量が著しく増加した。
引用:(※2)納豆の保存中における成分変化|福岡女子短大
「直接還元糖」は賞味期限切れぎりぎりがいちばん多くなります。
そのため、買ったばっかりの納豆より、発酵が進んだ納豆のほうがおいしく感じやすいと言われています。
ついに腐敗して食べられない納豆の特徴


納豆が発酵の過程を通り越し、雑菌が入って腐敗している場合のサインは、以下のとおりです。
一つずつ見ていきましょう。
どろっと溶けて、水っぽくなる
納豆は雑菌などが入り腐敗すると、どろっと溶けたり、水分が多くなりがちです。
腐敗が始まったばかりの時は、ちょっと水っぽく感じるだけかもしれませんが、腐敗が進むとどろどろに溶けてしまうこともあります。
水っぽくなってきたら、注意が必要です。



わたしはこの時点で食べるのを辞めるかも…ちょっと怖いですよね…。
アンモニア臭・腐ったチーズの臭いがする
納豆が腐っていると、ひどい異臭がします。
入ってしまった雑菌によって臭いは変化しますが、良くあるのはアンモニア臭や腐ったチーズの臭いです。
【胃臭の正体】
➀アンモニア
➁低級分岐脂肪酸(イソ吉草酸、イソ酪酸、2メチル酪酸など)
これらは納豆菌も作るので、腐っていなくてもアンモニア臭がすることもありますが、雑菌が入っているとさらにひどい臭いになることが多く、臭いがひどい時は食べないほうが賢明です。
アンモニア臭
=発酵過程で納豆菌などの発酵菌が作り出すアンモニアのにおい
腐ったチーズの臭い
=ロイシン、イソロイシン、バリンというアミノ酸が発酵の過程で科学変化をしたときの低級分岐脂肪酸のにおい



においはニガテな人は本当にニガテですからね…
カビが生えている
納豆が腐っていると、カビがはえます。
カビが生えてしまったら、もう食べられません。
納豆の周りの白くて薄い膜は、カビではなく、菌糸やアミノ酸などの旨味のもと。
カビと間違えやすいですが、カビではありませんのでご注意ください。



アミノ酸のチロシンも、カビと間違える人が多いです。笑
納豆を腐らせないための保存法


納豆は保存方法に気をつければ、そんなに腐りやすい食品ではありません。
長持ちさせたいなら、以下の保存法がおすすめです。
一つずつ見ていきましょう。
10℃以下の場所で保存する
納豆はなるべくはやく食べるのが鉄則です。
すぐ食べられないのであれば、開封はせず、必ず10℃以下の場所で保存しましょう。



開封したあとに半分だけのこしてラップかけておく人がたまにいますが、雑菌がかなり寄ってきやすくて危険!常温で長時間おいておくのもやめましょう。
しばらく食べないなら冷凍もOK
納豆をたくさん買ってしまって、1か月以上食べない可能性があるのであれば、冷凍保存することをおすすめします。
納豆は開封せずに、パックのままジップロックやフリーザーパックに入れて、冷凍保存しましょう。
食べるときは、そのまま自然解凍すれば食べられます。



納豆のパックをラップでぐるぐる巻きにして、ジップロックやフリーザーパックに入れたほうが風味が落ちないと言われますが、ずぼらなわたしは、ラップはやらないで入れちゃうことも多いです…笑 次の日に食べる分だけ、冷凍庫から冷蔵庫に移動しましょう。
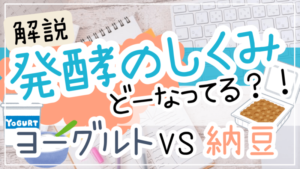
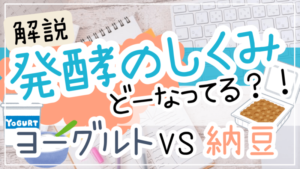
納豆のネバネバがニガテな人へ!糸をひかない納豆の作り方


力強い糸を引く納豆は、新鮮な納豆の証ではありますが、実際のところ苦手な人が多いのも事実です。
納豆の味は嫌いじゃないけど、糸だけどうにか減らせないか…と悩んでいる人も多いようです。
そんな方向けに糸を引かない納豆にする方法をご紹介します。
一つずつ見ていきましょう。
混ぜる前に醤油・タレを加える
納豆のネバネバを減らしたければ、かき混ぜる前に醤油やタレなどを加えるのがおすすめです。
もともと納豆には、納豆菌や旨味成分などのネバネバのもとが付着しています。
何も入れずに混ぜるとそれらが糸を引きネバネバを作りますが、醤油やタレを入れると納豆の周りのネバネバのもとが洗い流され、糸が引きにくくなります。
酢を加える
納豆に酢を加えると、納豆のネバネバが酸によって細かくなり、ネバネバというよりもふわふわなクリーム状の泡ができます。
納豆の人を引く様子がニガテな方は、酢によってふわふわな泡に変えてしまいましょう。



ただし、少しお酢の味は残るので注意してね。
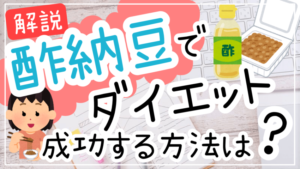
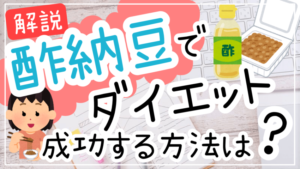
発酵を体系的に勉強したくなったら…
発酵ライフ推進協会オンライン校へ
\仕事に繋がる無料サポートもたくさん(*´ω`*)/
まとめ:納豆が糸ひかない&シャリシャリする原因は?腐ってる?


糸をひかない納豆は、腐っていることももちろんあり得ますが、必ずしも100%腐っているわけではありません。
しかし、納豆が製造されてから時間が経ち、保存している途中で発酵が進み過ぎ、味が落ちているのはたしかです。
納豆が糸を引かない理由は、以下のとおりです。
腐敗はしていなくても(雑菌が入っていなくても)、納豆は発酵しすぎると味が落ちます。
味が落ちる理由は以下のとおりです。
理由➀ 糸をひかなくなる/ねばりが弱くなる
→うま味のもと「γ-ポリグルタミン酸」が減る
理由➁ 噛むとシャリシャリする
→白い粒として見える、アミノ酸「チロシン」が増える
理由➂ 苦味がでる
→苦みのもとである、イソロイシン・バリン・リジンなどが増える
納豆が発酵の過程を通り越し、雑菌が入って腐敗している場合のサインは、以下のとおりです。
この状態が見られたら、もう食べられません。
参考にしてみてね。
発酵を体系的に勉強したくなったら…
発酵ライフ推進協会オンライン校へ
\仕事に繋がる無料サポートもたくさん(*´ω`*)/
参考文献
(※1)Gustatory sensation of (L)- and (D)-amino acids in humans
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22588481/
(※2)納豆の保存中における成分変化
https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=200902236318702948
(※3)納豆菌の糸引き不安定性|納豆学会
https://www.nattou.com/topics/is.html










