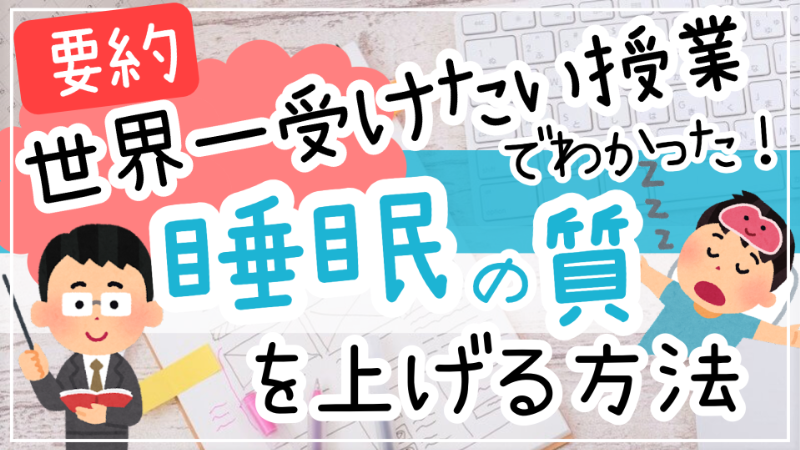【この記事で解決できるお悩み】
睡眠の質を上げる方法にはなにがあるの?
睡眠の質を上げるためにやってはいけないことってなに?
世界一受けたい授業で定期的に放送される「睡眠授業」をまとめて!



この記事では、こんなお悩みを解決します!
翌日の仕事や家事のパフォーマンスアップはもちろん、腸内環境を整え、健康的な体をキープするために「睡眠の重要性」が問われています。
厚生労働省の国民健康・栄養調査(※1)によると、「睡眠全体の質に満足できなかった」と答えた人は約20%と、約5人に1人は睡眠の不満を抱えているのだとか。
「仕事も家事も効率的にこなすために、睡眠の質を上げたい…」
そんな人たちのために、日本テレビ系列「世界一受けたい授業」では、定期的に「睡眠授業」が開催!
この放送がとてもわかりやすいと評判なんです。
今回は、そんな睡眠授業の第1回と第2回の放送内容の注目ポイントを総チェック!
ポイントをまとめながら、関連する科学論文を整理して、ご紹介します。
\ LDEライトを浴びるだけ!超簡単(*´▽`*)/


この記事を書いた人:
腸活研究家 長谷川ろみ
発酵食品にハマり、ダイエットなしで12㎏減。痩せたことをきっかけに腸を愛でる生活に目覚める。重度の便秘から解放され、腸活研究家として活動開始。今では発酵ライフ推進協会通信校校長を務め、昔の自分と同じ悩みを持つ方に向けて腸や菌のおもしろさを発信中。詳しくはこちら
睡眠の質とは?


「睡眠の質」という言葉をとても多く聞くようになりましたが、実は睡眠は「質」だけが良ければよいというものではありません。
睡眠に大事なのは、「量」と「質」。
世界一受けたい授業で講義を担当された、筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構機構長である、柳沢正史教授は、インタビューでこのように発言されています。
睡眠の質で最も重要なのは実は睡眠時間、つまり睡眠の量なんです。睡眠時間が足りていなければ、質を論じる意味がない。
引用:(※2)睡眠の未知を研究する「READY」な姿勢 柳沢正史|株式会社ゴールドウイン
柳沢正史教授
=筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構機構長
=睡眠検査サービスを提供するベンチャー企業「株式会社S’UIMIN」をスタート



睡眠の質ばかりが取り上げられるけど、その前に睡眠の量もちゃんと確保しないとね…。
質のよい睡眠の4条件
世界一受けたい授業で紹介された、柳沢正史教授が考える質のよい睡眠の条件は、以下のとおり。
【質のよい睡眠の条件】
1:眠りにつくまでの入眠時間が短い
2:寝ている途中で起きない(中途覚醒がない)
3:朝起きた時に深く眠れたと実感できる
4:日中に疲労感がない



ただ、よく眠れた!と思うだけではなくて、日中に疲労感がないことも重要なんですね。
質のよい睡眠づくりの基本は、以下の2点。
ひとつずつみてみましょう。
入浴のタイミングが重要
さまざまな研究から、睡眠と体温には深い関連があることが報告(※3、※4)されています。
入浴すると体の深部体温が上がり、約90分で元の体温に戻ります。
この体温が下がっていくタイミングで眠気が訪れるため、寝る予定時刻の90分前にお風呂から出ることを計算して入浴するのがよいのだとか。
【質の良い睡眠のための入浴ポイント】
お湯の温度:40~41℃程度(深部体温がきちんと変化する温度)
入浴タイミング:寝る時間の90分前に入浴が終えられるタイミングがベスト



温度が低すぎると、そもそも深部体温を上げられないのでよくないんだって。40~41℃が理想です。
生活リズムが重要
質の良い睡眠のためには、自分の体内時計に合わせた一定の生活リズムを保つことが重要です。
【質の良い睡眠のための生活のポイント】
・毎日同じ時間に寝て、起きる
・起きたら積極的に光を浴びる、寝るときは光を落とす
・自分の睡眠リズムや体内時計を意識して生活する
・睡眠に関連するホルモン「セロトニン」や「メラトニン」を分泌するためにタンパク質をとる など



ここで腸活が重要になります。腸内細菌は「セロトニン」や「メラトニン」づくりに貢献してるんだよ。
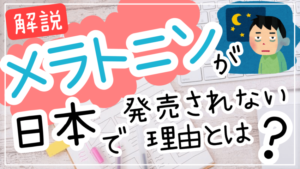
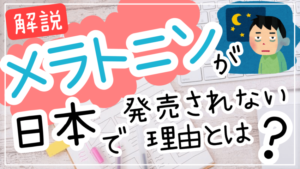
世界一受けたい授業では、自分の睡眠リズムや体内時計のリズムがよくわからない人のための、MEQテストが紹介されていました。
MEQ-SAテスト(※5)
=国立精神・神経医療研究センターが公表
=クロノタイプ(1日の中でどの時間帯に最も活動的になるかを示した時間帯特性)がセルフチェックできる
https://www.sleepmed.jp/q/meq/meq_form.php



わたしはやっぱり朝型…明らかに朝のほうがアイデアが浮かびやすいもんなぁ…笑 みなさんはどうですか?
睡眠の質を上げるためにやってはいけないNG習慣6選


2022年9月17日に放送された日本テレビ系列「世界一受けたい授業」では、柳沢教授の指導のもと、睡眠の質を上げるためにやってはいけないNG習慣が紹介されました。
詳しく見てみましょう。
「寝具」は定期的に新しくする
「世界一受けたい授業」では、「寝具」は定期的に新しくすることがおすすめされました。
その理由は、ベッドのマットレスの経年劣化。
マットレスは、長く使えば使うほど、同じ部分に負荷がかかり、凹んできます。
この微妙な凹みが、腰や背中などに負担をかけると、質の良い睡眠がとれなくなるのだとか。
・マットレスは、定期的に新しいものを調達する
・調達できないのなら、向きや裏表を変えて、負荷を均一に
・寝返りを邪魔しないマットレス・枕を意識する
・夏は通気性のよい寝具/冬は熱を逃しにくい寝具を使う



たしかにマットレスって、一部だけ変な形になるかも…もともと高反発マットレスを買っておくのもおすすめです。
\ 「スタンフォード式最高の睡眠」から生まれた高反発マットレス(*´▽`*)/
「ながら睡眠」に注意
「ながら睡眠」とは、何かをしながら眠りについてしまうこと。
ながら睡眠
=何かをしながら眠りについてしまうこと
=音楽を聴きながら|動画を見ながら|テレビを見ながらなど



これは、現代人はどうしてもやりがちだよね…ながら睡眠の翌日は、頭がちょっと痛かったりするので、わたしも注意してます。
ながら睡眠は、睡眠が浅くなるだけではなく、途中覚醒の原因にもなる悪習慣。
入眠する時には、きちんとすべての電源を消してから寝るのがおすすめです。



どうしても難しい人は、タイマー設定を使うなどするといいみたい。柳沢先生によると、完全なつけっぱなしよりは、多少は軽減されるようです。
寝るための「お酒」はNG
アルコールは、睡眠の質や量に大きく関係するとの報告(※6、※7)があります。
眠りにつきやすくなるアルコールは、一見睡眠の質を高めるように感じますが、睡眠全体を見ると質を悪化させる可能性が高く、注意が必要です。
【アルコールで起こる睡眠変化】
・寝つきが良くなる
・睡眠前半の徐波睡眠(脳も体も休んでいる、深い睡眠状態)が増える
・睡眠前半のレム睡眠(脳が活動し、体が休んでいる浅い睡眠状態)が減る
・睡眠後半の徐波睡眠(脳も体も休んでいる、深い睡眠状態)が減る
・睡眠後半のレム睡眠(脳が活動し、体が休んでいる浅い睡眠状態)が増える
・中途覚醒が増える



睡眠後半の悪影響は、アルコールが覚醒作用があるアセトアルデヒドに変化することに関係があると言われています。
アセトアルデヒド(※8)
=アルコールから作られる物質のひとつ
=フラッシング反応(顔が赤くなる、吐き気、動機、眠くなるなど)や二日酔いの原因になる
=動物実験では発癌性、ヒトでは食道癌の原因となるという報告も



お酒を飲むときは飲みすぎないのはもちろん、ちゃんとお酒が抜けてから寝るのがベスト!
寝る前の「光」に注意
寝る前の光の質は、睡眠の質や量に大きく関係するとの報告(※9)があります。
有名なのは、スマートフォンなどから発せられるブルーライトです。
ブルーライトは、脳を昼間の状態だと勘違いさせてしまうため、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が妨げられる可能性があります。
さらに、世界一受けたい授業では、リビングなどの部屋の光も重要だと紹介されました。



たしかにスマートフォンよりぜんぜん大きな光が入ってくるもんね…。
九州大学の報告(※9)によると、睡眠ホルモンであるメラトニンの濃度と光の色は関連があり、寝る前は青い光よりも赤い光のほうが睡眠を妨げないことが分かっています。



寝る前はなるべく薄暗くして、赤い光を活用するのがおすすめです。
\ LDEライトを浴びるだけ!超簡単(*´▽`*)/
睡眠中、「エアコン」は切らない
睡眠の質を高めたいなら、部屋の温度管理も重要です。
特に世界一受けたい授業では、実際に柳沢先生がしている習慣として、エアコンをつけっぱなしにして寝ることをおすすめしていました。
・エアコンはタイマー設定ではなく、そのまま朝までつけっぱなしに
・自分が快適に感じる温度を見つけるのが重要
・夏でも冬でも掛け布団は必ず使う
・靴下は温度管理が難しいので、どうしても必要ならレッグウォーマーを使う
また、冬の間は使ってしまいがちな靴下ですが、世界一受けたい授業ではNGとのこと。
手足から逃げる熱をコントロールしにくくなるので、靴下は履かずに、レッグウォーマーを使うのがおすすめです。
「午後3時以降の昼寝」はNG
質の良い睡眠のために、時に昼寝をするのは悪いことではありません。
ただ、仮眠は必ず午後3時までに終えるようにすることが、世界一受けたい授業のおすすめです。
さらに仮眠時間は、20分以内にすることも重要なポイントです。
【質の良い睡眠のための昼寝のコツ】
・浅い眠りで終えられる20分以内にする
・夜の眠りを妨げないように、午後3時までに昼寝は終える
・昼寝前にコーヒーを含むと、カフェインの効果ですっきり目覚められるかも?



飲んでから20~30分後にカフェインの効果があらわれるコーヒーを上手く使えば、目覚まし時計のように上手くタイミングが計れるようです。ただ…私はやってみたけど難しかったので、人によるかも?笑
睡眠の質を上げるための環境づくり5選


2023年3月11日に放送された日本テレビ系列「世界一受けたい授業」のテーマは、「睡眠授業第2弾」!
柳沢教授の指導のもと、睡眠の質を上げるための環境づくりのコツが紹介されました。
詳しく見てみましょう。
「緑」を配置する
世界一受けたい授業でわかった、質の良い睡眠を作る部屋に重要なのは「緑」です。



世界一受けたい授業で出てきた「緑」の意味は、観葉植物を表しています。
【観葉植物のメリット】
・視覚的に安心感が得られる
・蒸散作用(湿度調整)が期待できる
・カビを除去する作用が期待できる
・空気清浄作用が期待できる
・マイナスイオンの量が増え、副交感神経を優位にする
・複合効果によって、作業パフォーマンスが上がる可能性あり
農林水産省林野庁のホームページで紹介されている研究報告(※10、※11)によると、樹木からの揮発性物質「フィトンチッド」には、さまざまな健康増進効果があることが期待されています。
フィトンチッド
=ロシア語で「植物の揮発成分が持つ殺菌作用」という意味の言葉
=植物が持っている自分の体を外敵から守るための揮発成分
フィトンチッドの研究内容
・森林の中で歩くと都市で歩くより、リラックス状態を示す副交感神経活動が2倍になる
・森林の中で座ると都市で座るより、リラックス状態を示す副交感神経活動が1.5倍になる
・森林の中で座ると都市で座るより、ストレスホルモンのコルチゾール濃度が13%下がる



観葉植物の種類によっても、リラックス効果の種類が違うんだって!自分にあった、睡眠の質を上げる植物、ぜひ探してみて。
| 緑の種類 | 期待効果 |
|---|---|
| サンスベリア | 二酸化炭素を減らし、酸素濃度を高める |
| オーガスタ | 蒸散作用(加湿効果)がある |
| イングリッシュアイビー | カビを除去する作用がある |
| アレカヤシ | 蒸散作用(加湿効果)、空気清浄作用がある |



うちにもサンスベリアがあるよ!育てやすくておすすめです。
\ パーソナル診断で自分に合った緑が選べる(*´▽`*)/
快適な「室温」をキープする
世界一受けたい授業でわかった、質の良い睡眠を作る部屋に重要なのは「室温」です。
なんと、解説者の柳沢先生の家には10個も温度計が置いてあるとか。



すごい!!
冬は21度~22度、夏は24度を基準に室温を安定させるのが快眠のコツとのことでした。
「照明」は最小限に
質の良い睡眠を作る部屋のポイントの3つ目は、照明です。
夜の時間は、なるべく照明を最小限まで落とすこと。
そして、できれば間接照明にするのがおすすめです。
【照明の調整方法】
・寝る3時間前には、なるべく照明を最小限まで落とす
・間接照明にするのがおすすめ
・照明の色は青系よりも赤系にする
・寝る前のスマホ・PC利用はひかえる
九州大学の報告(※9)によると、睡眠ホルモンであるメラトニンの濃度と光の色は関連があり、寝る前は青い光よりも赤い光のほうが睡眠を妨げないことが分かっています。



個人的には、光を落とすだけでかなり眠くなるので、光を赤系にするのは気を付けています。睡眠の質を上げる方法の中でも一番効果があったかも…。
\ LDEライトを浴びるだけ!超簡単(*´▽`*)/
「大きな窓」がある部屋がおすすめ
質の良い睡眠を作る部屋のポイントの4つ目は、寝室を「大きな窓」がある部屋にすることです。



引っ越す時のポイントは、「大きな窓」にするのがおすすめ!わたしは窓にこだわったよ。
「夜の時間は照明を最小限まで落とし、朝になったら日の光をたっぷり入れる」
これが、体内時計を狂わせない最大のポイントです。



わたしは、日の光とともに起きることができるSwitchBotカーテンも使ってます。笑


パートナーと「ベッドは別々」に
質の良い睡眠を作る部屋のポイントの5つ目は、ベッドは1人1台を使うこと。
世界一受けたい授業によると、基本的にベッドは1人1台がベスト。
なぜなら、2人以上が1つのベッドで寝ていると、どうしても寝返りをうった時に振動が伝わり、一緒に寝ている人の快眠を妨げてしまうからなのだとか。



眠りが浅い人は、特に絶対気が付いちゃうよね…。仲良しなのはよいですが、質の良い睡眠のためを考えるなら、ベッドは別々に!
\ 「スタンフォード式最高の睡眠」から生まれた高反発マットレス(*´▽`*)/
まとめ:世界一受けたい授業でわかった睡眠の質を上げる方法


2022年9月17日に放送された日本テレビ系列「世界一受けたい授業」では、柳沢教授の指導のもと、睡眠の質を上げるためにやってはいけないNG習慣が紹介されました。
また、睡眠授業の第2回となる、2023年3月11日に放送された日本テレビ系列「世界一受けたい授業」では、柳沢教授の指導のもと、睡眠の質を上げるための環境づくりのコツが紹介されています。
この両方が自分の生活習慣に落とし込めれば、睡眠の質が劇的に変わるはず!
睡眠の質が変われば、寝ている間に活動が活性化する腸内細菌も元気になり、体のバランスがさらに整えられること間違いなしです。
それでも眠れない人は、睡眠ホルモン「メラトニン」が出やすくなる方法やメラトニンサプリについての記事も読んでみてね。
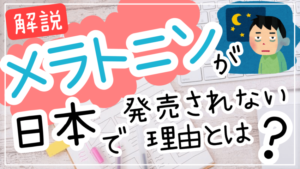
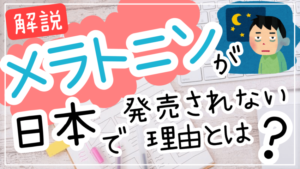
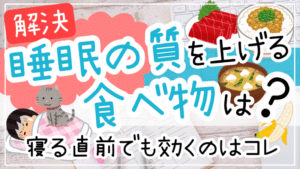
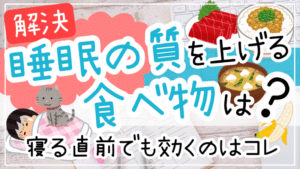
参考になれば幸いです。
\ LDEライトを浴びるだけ!超簡単(*´▽`*)/
参考文献
(※1)令和元年国民健康・栄養調査|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000687163.pdf
(※2)睡眠の未知を研究する「READY」な姿勢 柳沢正史|株式会社ゴールドウイン
https://www.goldwin.co.jp/neutralworks/info/journal/20221118people/
(※3)入浴と睡眠の関連に関するシステマティックレビュー
https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2013/133061/201315046A_upload/201315046A0009.pdf
(※4)亀井雄一,内山真|快眠法
https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=200902201210101320
(※5)MEQ-SAテスト|国立精神・神経医療研究センター
https://www.sleepmed.jp/q/meq/meq_form.php
(※6)Alcohol and sleep I: effects on normal sleep
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23347102/
(※7)Sleep, sleepiness, sleep disorders and alcohol use and abuse
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12530993/
(※8)アセトアルデヒド|厚生労働省
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/alcohol/ya-005.html
(※9)夜の青色光と赤色光の生理作用:測定項目間の違いと印象評価との関連性
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpa/22/2/22_69/_pdf/-char/ja
(※10)森林の有する多面的機能について |農林水産省林野庁
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/tamenteki/con_2_6.html
(※11)The physiological effects of Shinrin-yoku (taking in the forest atmosphere or forest bathing): evidence from field experiments in 24 forests across Japan
https://environhealthprevmed.biomedcentral.com/articles/10.1007/s12199-009-0086-9