【この記事で解決できるお悩み】
寝る前の時間、スマホ以外何する?
なんで寝る前にスマホをいじっちゃダメなの?
睡眠の質を高めるスマホ断ちを成功させるコツを教えて!



この記事では、こんなお悩みを解決します!
睡眠中は、腸のおそうじ時間。
消化活動を円滑にして、腸内細菌にビタミンやホルモンの材料を作ってもらうためにも、睡眠の質を高めることは重要です。
「寝る前はスマホはいじらないほうがいい。」「寝る前のブルーライトは眠れなくなる。」
そうわかっていても、実際スマホ以外に何をしたらよいかわからないという方も多いみたい。
そこで今回は、スマホ断ちした時におすすめの夜活アイデアを総まとめ!
睡眠の質を高めるスマホ断ちのコツと一緒にご紹介します。
\ LDEライトを浴びるだけ!超簡単(*´▽`*)/


この記事を書いた人:
腸活研究家 長谷川ろみ
発酵食品にハマり、ダイエットなしで12㎏減。痩せたことをきっかけに腸を愛でる生活に目覚める。重度の便秘から解放され、腸活研究家として活動開始。今では発酵ライフ推進協会通信校校長を務め、昔の自分と同じ悩みを持つ方に向けて腸や菌のおもしろさを発信中。詳しくはこちら
寝る前、スマホ以外何する?


寝る前、スマホ以外にするおすすめの夜活は、以下のとおり。
一つずつ見ていきましょう。
読書をする・オーディオブックを聞く
寝る前にスマホの代わりにやることの代表案と言えば、読書です。



活字を読んでいると、自然と眠くなるという人も多いよね。
自分の目的にあったインプットが効率的にできる読書は、寝る前のスキマ時間にぴったり。
読んでいるうちに自然と眠くなり、心地よい眠りをいざなってくれると感じる人もいるでしょう。



この自然と眠くなる効果には、科学的な根拠もあるんです。
イギリスにあるサセックス大学の報告(※1)によると、たった6分の読書がストレスレベルを2/3以上軽減するのだとか。
・6分の読書がストレスレベルを2/3以上軽減
・読書のストレス軽減効果は、散歩や音楽を聴くこと、座ってお茶を飲むことより高い
読書は、心拍数を下げ、筋肉の緊張を和らげて、副交感神経を優位にしてくれます。
そのため、自然と眠くなりやすいのです。
さらに最近は、耳で聞くことができる本、オーディオブックもたくさんの種類が出ています。
聞きながら入眠すると、記憶にも残りやすいため、スマホをいじる時間よりよっぽど質の良い情報が得られます。



やっぱりスマホ断ちの代替品の王道は、読書ですよね。わたしも読書してるよ。
日記・TODOリストを書く
近年、寝る前にスマホの代わりにやることとして注目されているのは、日記・TODOリストを書くことです。



文字を書くことによる、ストレスレベルや心理的な影響に関する研究が、ここ数年で増えているようです。
夜寝る前に1日にあった良かったこと・感謝したことなどのポジティブな出来事を振り返り、実際にノートに書いてみるだけで、不思議と心の中がポジティブに。
書くことと心の健康は、大きく関係しているという報告(※4)があります。
【ポジティブな内容を書くと起こる心の変化】
・主観的な幸福感が高まる
・よく眠れる
・よく動ける
・身体的な不調が減る など
さらにすごいのが、たとえポジティブな内容がかけなくても心配する必要がないこと。
ネガティブな内容でもなにも書かないよりは、健康度が高くなり、うつ病や不安症のレベルが低下することが報告(※4)されています。



毎日寝る前に日記をつけて、明日やりたいこと(TODOリストなど)を見直すだけで、睡眠の質も、自己肯定感も、健康レベルも上がるなんて、すごくない?スマホのメモ機能に書いてブルーライトを浴びていたら意味がないので、きをつけて!笑
勉強をする・暗記をする
寝る前のスマホ断ちに役立つ活動であり、スキルアップにもなるのが、勉強です。
ハンブルグ大学の研究(※6)によると、単語の暗記をする際、単語学習をした後に起きたまま試験をうけるのと、3時間深い睡眠をとってから試験を受けるのでは、成績の向上率が全く違ったのだとか。
A:単語の暗記→3時間の深い睡眠→試験→成績の向上率32.4%
B:単語の暗記→3時間起きたまま→試験→成績の向上率16.5%
さらに、浅い眠りをとってから、勉強し、再度浅い眠りをとった場合は、成績の向上率が悪かったそうです。
C:3時間の浅い睡眠→単語の暗記→3時間の浅い睡眠→試験→成績の向上率11.0%
D:3時間の浅い睡眠→単語の暗記→3時間起きたまま→試験→成績の向上率12.2%



この報告を見ると、暗記学習は寝る前にするのが定着率がよさそうです。英語の単語の勉強とか、試験勉強でも丸暗記系が相性よさそう…
ラジオ・Voicy・YouTubeを聞く
スマホの代わりにやることとして4番目におすすめするのは、ラジオ・Voicy・YouTubeなどのコンテンツを耳で聞くことです。



コロナ禍で、耳から消費するコンテンツは発達した印象がありますね。わたしもラジオ・Voicyファンです。寝る前はもちろん散歩中もお世話になってるなぁ…
さらに、YouTubeで音楽を聴くのもおすすめです。
プレイリストを作って公開してくれている人もいるので、リラックス効果のある音楽やヒーリングミュージックなど、種類が豊富で、お気に入りのリラックス音を選ぶことができます。



音楽の種類が豊富でいいよね…!
腸もみ・ストレッチで体をほぐす
スマホの代わりにコンテンツを消費するのもよいですが、翌日の体の調子を整えるために、腸もみやストレッチをするのも有効です。



特に入浴後に腸もみをすると、お腹がぐるぐると音をたてて動き出すこともあって、効いてる~って思えます。笑
がっつりハード系のストレッチをやるのは疲れてしまう…という方でもできるのが腸もみです。
それこそ、ラジオ・Voicy・YouTubeなどのコンテンツを耳で聞きながらできるので、おすすめです。



自分の腸にあったもみ方がわかってきたら、動画どおりにやらなくてもOK。自分の好きな音楽を聴きながら、毎日の習慣としてトライしてみて。
瞑想をする
寝る前にスマホの代わりにおすすめする最後の方法は、瞑想です。
瞑想というと特別なことのように感じますが、要は心を静めて無心になることです。



いちばんかんたんな瞑想方法だと、目をつぶってじっとして、視覚や聴覚に集中し、ゆっくりと呼吸するだけでOK。難しく考えなくても大丈夫です。
アロマキャンドルをたいて、自分なりのリラックス空間を演出するのもおすすめです。
瞑想プログラムを4カ月間体験する前と後で、ストレスホルモンであるコルチゾール値を検査したところ、瞑想プログラム後に数値が下がったという報告(※8)があり、科学的根拠も含めて、瞑想は注目されています。
\ LDEライトを浴びるだけ!超簡単(*´▽`*)/
スマホ断ちが大事な理由





スマホ断ちしたほうがいいってよく言うけど、一体なんで?



スマホ断ちがおすすめされるのには、ちゃーんと科学的な理由があるの。
寝る前にスマホを使うのが良くないとされる理由は、以下のとおり。
一つずつ見ていきましょう。
単純に睡眠時間が減るから
夜寝る前にスマホを使うと、ついつい見続けてしまい、無駄な時間を増やしてしまう恐れがあるからです。
北海学園大学の学生のスマートフォン使用状況と健康に関する調査研究(※9)によると、53.6%の人がスマートフォンの使用で睡眠時間が減ったと回答しています。
【スマートフォンの使用で減ったものランキング】
睡眠時間:53.6%
勉強時間:46.4%
読書時間:31.1%



なんと…1位は睡眠時間。重要な時間がスマホで奪われているってことだ…
寝る前にベッドの中でスマートフォンをいじり始めると、知らぬ間に15分、30分、1時間と、ついついSNSやコンテンツを見続けてしまいます。
そのため、寝る前のスマホは健康を害したり、美容に良くないとされ、あまり推奨されません。
睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が減るから
夜寝る前にスマホを使うと、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が減り、ますます眠れなくなってしまうという報告(※10)があります。
メラトニンとは、私たちの体を適切なタイミングで眠りにいざなってくれるホルモンです。
このホルモンの分泌が明らかに減ってしまうのが、スマートフォンをはじめとする電子デバイスの光です。
・電子デバイスを使って読書するとメラトニン分泌量は50%以下に減る



50%以下!?これはやばい…。眠りたい時に眠れない体になりたくなかったら、夜寝る前にスマホを使うのはやめましょう。
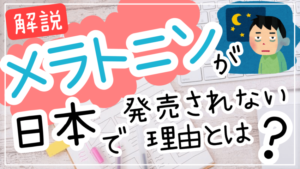
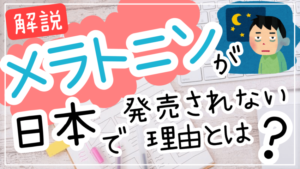
神経伝達物質「ドーパミン」の過剰分泌につながるから
夜寝る前にスマホを使うと、神経伝達物質「ドーパミン」を過剰に分泌して、脳を活性化させてしまうと言われています。
ドーパミン(※11)
=神経伝達物質の一つ
=脳内報酬系の活性化に役立つ
厚生労働省のホームページ(※11)によると、ドーパミンの過剰分泌はパーキンソン病や統合失調症と関わりがあるようなので注意が必要です。
スマホ断ち成功のコツ


寝る前のスマホが良くないのはわかっていても、それ以外何するかがイマイチ出てこない人も多いはず。
習慣を変えることをめんどくさがっていると、なかなかスマホ断ちはできません。
ここでは、スマホ断ちに挫折しないように、スマホ断ち成功のコツをまとめてみました。



私が実際に体験した方法だよ!
詳しく見てみましょう。
「if-thenプランニング」を活用する
if-then プランニングとは、社会心理学者のハイディ グラント ハルバーソン博士が提唱した目的達成のためのテクニックのひとつです。



寝る前のスマホ断ちだけじゃなくて、習慣づくり全般に使われる考え方・テクニックだよ。
if-then プランニングは、「もし●●だったら、▲▲する」とあらかじめ決めておき、それを実行する方法です。
(if)もし●●だったら
(then)▲▲する
例えばスマホ断ちの場合は、「スマホが使いたくなったら、コレをする」というルールをあらかじめ作っておくということ。



「スマホが使いたくなったら、日記を書く」とか、「スマホが使いたくなったら、音楽をかける」とか、そういう自分だけの独自ルールね。
ルール化しておくことで、同じ活動を続けやすくなります。
「入浴時間」をコントロールする
質の良い睡眠のためには、入浴時間を入眠の90分前までに終えるのが良いとされています。
この時間をしっかり守り、90分以上の時間をかけないようにすると、自然とスマホを使う時間が削られていき、結果使わないで済むようになります。



私はこの90分ルールの間に家事をしたり、腸もみをしたり、読書をするようにしているので、意外とスマホのことを忘れることができてます。良い方法かも?!
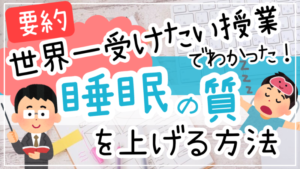
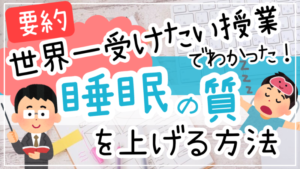
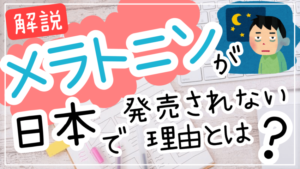
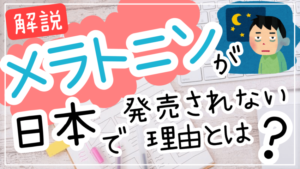
まとめ:寝る前、スマホ以外何する?スマホNGの理由


寝る前、スマホ以外にするおすすめの夜活は、以下のとおり。
なんで寝る前にスマホを使うのが良くないのかは、とてもシンプルです。
次の日の仕事や家事のパフォーマンスを下げたくなかったら、寝る前のスマホ断ちに挑戦してみましょう。
成功のポイントとなる考え方は、以下の2つ。
参考にしてみてね。
\ LDEライトを浴びるだけ!超簡単(*´▽`*)/
参考文献
(※1)Reading can help reduce stress
https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/5070874/Reading-can-help-reduce-stress.html
(※2)Reading can help reduce stress, according to University of Sussex research | The Argus
https://www.theargus.co.uk/news/4245076.reading-can-help-reduce-stress-according-to-university-of-sussex-research/#comments-anchor
(※3)When doctors prescribe books to heal the mind
https://www.bostonglobe.com/ideas/2013/12/22/when-doctors-prescribe-books-heal-mind/H2mbhLnTJ3Gy96BS8TUgiL/story.html
(※4)自発的な筆記行動と心身の健康との関係性
http://repository.kyusan-u.ac.jp/dspace/bitstream/11178/101/1/kokubun57-5.pdf
(※5)心理社会的ストレス対処のための筆記表現法の応用可能性の検討
https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/13j076.pdf
(※6)Effects of early and late nocturnal sleep on declarative and procedural memory
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23968216/
(※7)Practice with sleep makes perfect: sleep-dependent motor skill learning
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12123620/
(※8)Effects of the Transcendental Meditation program on adaptive mechanisms: changes in hormone levels and responses to stress after 4 months of practice
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9226731/
(※9)学生のスマートフォン使用状況と健康に関する調査研究
http://hokuga.hgu.jp/
(※10)Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness
https://www.pnas.org/doi/pdf/10.1073/pnas.1418490112
(※11)ドーパミン|厚生労働省
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/alcohol/ya-047.html










