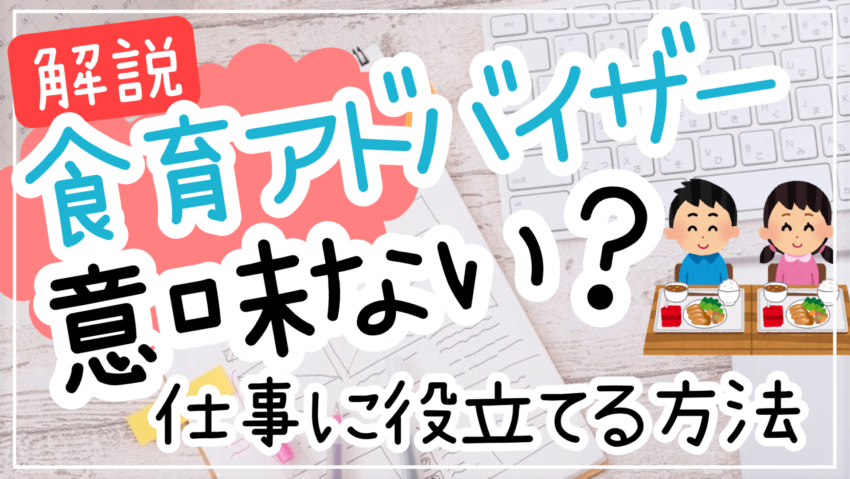【この記事で解決できるお悩み】
・食育アドバイザーをとっても、意味ないってホント?
・食育アドバイザーは、役に立たないと言われる理由は?
・ゆくゆく飲食や子ども関連の仕事がしたいんだけど、食育アドバイザー資格が役立つか知りたい!



この記事では、こんなお悩みを解決します!
食育アドバイザー資格は、飲食と教育がテーマ。
そのため、子育て中のママさんや主婦の方に人気の資格です。
2005年に食育基本法が制定されてから、ますます「食育」が注目され、食育の専門知識を持った人の育成が必要になったと同時に、食育の資格も増えました。
でも、インターネット上では、食育アドバイザーなんて「とっても、意味ない」、「役立たない」、「お金と時間の無駄遣いになる」とおっしゃる人も多いようです…。
そこで今回は、食育アドバイザーは取得しても意味ないというウワサは本当か、徹底調査!
実際の取得者の口コミを確認しながら、どんな人なら食育アドバイザー資格を仕事に役立てることができるのか、おすすめの人を整理してみました。
発酵を体系的に勉強したくなったら…
発酵ライフ推進協会オンライン校へ
\仕事に繋がる無料サポートもたくさん(*´ω`*)/


この記事を書いた人:
腸活研究家 長谷川ろみ
発酵食品にハマり、ダイエットなしで12㎏減。痩せたことをきっかけに腸を愛でる生活に目覚める。重度の便秘から解放され、腸活研究家として活動開始。今では発酵ライフ推進協会通信校校長を務め、昔の自分と同じ悩みを持つ方に向けて腸や菌のおもしろさを発信中。詳しくはこちら
結論:食育アドバイザーが役に立たないかどうかは、人による!


結論から言うと、食育アドバイザーは役立たないわけではありません。
しかし、あたりまえですが、取得目的によってはあまり役立ちません。
食育アドバイザー資格が役立つかどうかは、人によるというのが正直な答え。
食育アドバイザー資格に何を期待するのか、その取得目的によって、意味のあるなし、役立つか役立たないかが決まります。



えー--。あいまいな答えやだなぁ…



この世の全員にとって役立つ資格なんてないから、あたりまえと言えばあたりまえなんだけどね。
特に、食育アドバイザーは、栄養学から食品衛生、社会生活上の食品流通まで、食事に関する知識を広く網羅した資格です。
内容が幅広ければ幅広いほど、専門性は薄まるので、食育アドバイザーをお仕事に使おうとすると期待通りにならない可能性があります。



仕事というより、自分や家族、そして近くにいる大事な人の健康を守るための知識が体系的に学べる資格という意味合いが強いんです。


取得目的別!食育アドバイザーは役立つ?役立たない?


食育アドバイザーの取得目的には、大きくわけて2つあります。
ひとつずつ見ていきましょう。
自分や家族の健康のために役立つのか?
食育アドバイザーを取得する目的の多くは、自分や家族の健康のためです。
食育アドバイザーは、その名前に「食育」と入っているので、子どもに対する知識だけを学ぶ資格であると誤解しがちですが、そうではありません。
食育アドバイザー資格の勉強をすると、自然と基本的な食に関する知識を広く浅く学ぶことができます。
自分や家族の健康のためを考えた時に、食育アドバイザー資格にたどり着き、食育アドバイザー資格をきっかけに食の勉強をはじめる方はとても多いのです。



ここでちょっとSNS上の口コミもご紹介しましょう。



自分や家族の健康のためなら、すごく役立ちそうだし、満足度も高いみたい!旦那さんに長生きしてもらうためなんて…愛だなぁ…!
仕事(キャリアアップ、転職、就職、起業)のために役立つのか?
食育アドバイザーを取得する目的として、もうひとつ多いのは仕事に活かすためです。
仕事に活かすと言っても、いろんな方法があります。
今務めている会社のキャリアアップや就職条件として、食育アドバイザーが設定されていることもあれば、知識を体系的に得るために起業を目指す方が取得することも。



食育アドバイザーは意味がない、役立たないと言われるのは、主にこっち。「仕事に役立つ」と思っていたら役立たなかったという人が多いの。
栄養士をとるのが難しいから、食育アドバイザーをとろうとする人はとても多いようです。
また、キャリアアップにつながるからという取得目的で、食育アドバイザーを目指す人もいます。



でも…食育アドバイザーを仕事に活かすのはそんなにかんたんではなさそうです。(理由はあとで説明します!)仕事につなげる食の資格なら、発酵食に関連する資格もあるよ。
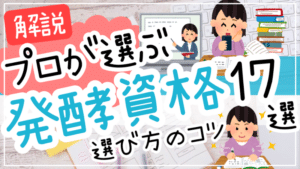
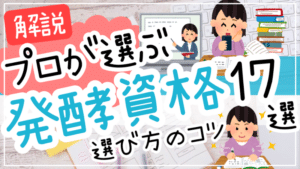
食育アドバイザーは意味ない&役に立たないと言われる理由


食育アドバイザーは意味ない&役に立たないと言われる理由は、以下の3つです。
ひとつずつ見ていきましょう。
理由➀ 国家資格ではなく、民間資格だから
食育アドバイザーは、国家資格ではなく、民間資格です。
もちろん、今や国家資格をとったからといって、なにもしなくても仕事が舞い込む時代ではありません。
それは、国家資格である、弁護士、会計士、管理栄養士でも、同じこと。
業務独占資格と呼ばれる一部の国家資格以外は、キャリアアップや転職にそこまで有利になりません。
業務独占資格
=資格を取得している人だけが業務を行える資格
=資格を有していない人が業務を行うのは法律違反になる
=例:医師、看護師、あん摩マッサージ指圧師、作業療法士、行政書士など



あん摩マッサージ指圧師も業務独占資格なんですね~実はいろいろあるんだよね。一度、総務省の「業務独占資格制度一覧」を見てみると、参考になるかも!
でも、就職や転職をする時に、国家資格を持っていると応募できる就職先が増える(国家資格が応募条件になっている)ことはあり得ます。
しかし、食育アドバイザーは取得したからと言って、就職先が約束されるわけではありませんし、応募条件になっている仕事があるわけでもありません。
もちろん、食育アドバイザー資格は履歴書に書くことができるので、基礎的な食に関する知識を持っていることをアピールすることは可能です。
質問:資格名は履歴書に書いても良いのですか? 答え:履歴書に書いていただくことができます。
引用:一般社団法人日本能力開発推進協会 よくある質問



履歴書にはかけるけど、だからと言って面接に受かるってこともないだろうしなぁ…
もちろん民間資格だからダメというわけではないですが、いまだに「国家資格に比べると信頼性は低い」と考える人が多いようです。



まさにそういうことですよね…。
理由② 民間資格の中でも、さらに専門性が弱い資格だから
食育アドバイザーは、同じ食に関係する民間資格の中でも、ずば抜けて試験範囲が広い資格です。
その試験範囲とは、以下のとおり。
【食育アドバイザー受験科目】
・食育の目的
・食欲をはぐくむ重要性
・一日3回の食事の重要性
・共食の重要性と孤食の問題点
・おやつの重要性
・食育マナー
・フード・マイレージ
・世界の食料事情
・食料自給率
・学校給食と外食の役割
・行事食と郷土料理
・栄養と栄養素
・栄養素の種類と働き
・食事摂取基準
・年代による望ましい食事
・一日に必要なエネルギー量
・食事バランスガイド
・バランスのよい食事
・バランスのよい献立 など



やっぱり広いですね…郷土料理まで学ぶのかぁ…!
食生活アドバイザーは、2005年7月に施行された食育基本法に基づいています。
食育基本法
=2005年7月15日に施行
=国民の健康と豊かな人間性を育むことを目的として作られた法律
何かのプロになるための専門知識や技術を学ぶのではなく、食を楽しみ、充実させながら、ちゃんと健康的な栄養バランスを守ることを目指します。



自分や家族の食生活を守るためにはとても役立つけど、広く浅く知識を確認するような資格なのでお仕事にはなりにくいんですよね…。
同じ民間資格でも食育アドバイザーとは違い、専門性が高く、狭く深く知識をつける資格もあります。
このような専門性の高い資格のほうが、仕事に繋がりやすく、ご本人の発信活動次第では人脈もできやすい傾向にあります。
| 専門性が低い資格 | 専門性が高い資格 | |
|---|---|---|
| 資格例 | 食生活アドバイザー | 発酵・漢方・ハーブ・腸活など テーマがある食関連資格 |
| 学習範囲 | 広い | 狭い |
| 仕事への繋がりやすさ | 低い | 高い |



どっちもそれぞれメリットとデメリットがあります。テーマがある食関連資格のほうが仕事に繋がりやすい分、取得コストが高いイメージがあるなぁ…。



仕事に繋がる発酵の資格が気になる人は、こちらの記事も読んでみてね。
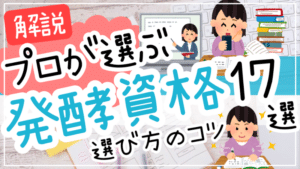
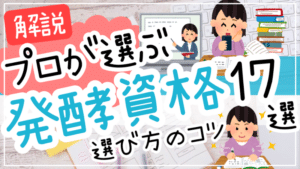
理由➂ 日常生活で知識を活かすのに最適な資格で、資格をとったら終わりだから
食育アドバイザーは、通常、資格をとったら終わりです。



試験で合格して、資格がもらえたら、満足しちゃうんだよね…
例えば管理栄養士などの国家資格は、資格をとってからが本番です。
資格をとってから就職・転職活動が本格的にはじまるケースが多いのは、資格が応募条件になることも少なくないからです。
一方で、食育アドバイザーはその資格だけを持って就職・転職活動を始めるということは少ないでしょう。
国家資格だけではありません。
民間資格の中には、資格をとった後に資格取得者限定のコミュニティが用意されていて、仲間を作ることができたり、講師を目指す方向けの無料講座への参加権利がもらえる資格もあります。
食育アドバイザーは、資格をとること=スタートではなく、資格をとること=ゴールの意味合いが強い資格なので、自分で取得後の計画を積極的に練らないと、資格をとって終わりになってしまいます。
※ただし、一部の保育士や介護職などでは、企業内の制度として食育アドバイザーがスキルアップに使える場合もあるようなので、資格と類似するお仕事をすでにされている方は、企業に確認してみる必要があります。



この場合は、かなりラッキーかも!会社によっては、資格をとるとボーナスがあるところもあるらしいよ。
仕事に活かしたいという強い気持ちがあり、国家資格の取得が難しいというご事情があるなら、せめて資格をとって終わりにならない、仕事につなげやすい民間資格を探してみるのもおすすめです。



資格取得後に無料で講師養成講座が受けられたり、オンラインコミュニティで定例の勉強会がある資格もあるので、気になる方はいろいろ探してみてね。


食育アドバイザーを仕事に役立てる方法


食育アドバイザーを仕事に役立てるのは、かんたんなことではありません。



目的が仕事に役立てることでなければ、体系的に生活知識が学べるという意味で、とても有用な資格です。
しかし、諦めるのはまだ早いです。
食育アドバイザーを仕事に役立てたい人は、戦略的に資格を取得し、取得後から目的達成のための道のりを整理する必要があります。
参考までに、仕事に役立てるための3つの方法を整理してみましょう。



あくまでこういう方法もあるよ!という意味です。自分の場合は、どうやったら食育アドバイザーが仕事に活かせるか、自分で整理する必要があるよ。参考にして、考えてみて!
方法➀ 履歴書に記入して積極的にアピールする
食育アドバイザーは、履歴書に記入することが認められている資格です。
就職・転職活動の際には、履歴書に記入して、積極的にアピールしましょう。
また、SNS等で情報発信をする際にも食育アドバイザーであることを記載すると、思わぬメリットがあるかもしれません。
自分と同じように食育に興味がある人とのつながりが生まれたり、関連する企業とのつながりができることもあります。



わたしも「発酵ライフアドバイザー」として発信活動をし、企業からお仕事のお誘いをいただくことがありますよ。アピールするのは大事かも…?
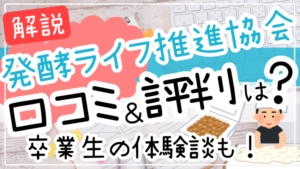
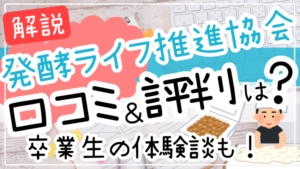
方法➁ 他の資格と組み合わせて、専門性を高める
食育アドバイザーは、民間資格の中でも出題範囲が広く、専門性が高いとは言えない資格です。
食生活アドバイザー取得後にもう少し範囲が狭く深い専門的な知識が得られる資格をとることで、自分だけの個性的な仕事に繋がる可能性が高まります。
民間資格であっても、専門的な資格は多いので、自分の将来の計画に合わせて、どんな知識をつけたいか整理してみましょう。
発酵食品系の資格
漢方・薬膳系の資格
腸活・腸もみ系の資格
スポーツ・トレーニング系の資格など



発酵系のおすすめ資格や腸活・腸もみ系の資格が気になる人は、こちらの記事も読んでみてね。
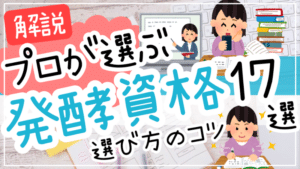
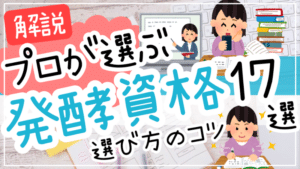
方法③ 実務経験を積んだり、人脈を得る別の方法を考える
食育アドバイザーは、どうしても取得したら終わりになりやすい資格です。
直接お仕事を得るのが難しいのであれば、まったく別の方法で実務経験や人脈を得る努力をすることが必要です。
・子どもや食に関する、SNSやブログなどを使った発信活動
・子どもや食に関する、イベントや勉強会、セミナーへの参加
・子どもや食に関する、ボランティア活動への参加など



資格に頼りすぎず、自分でどんどんチャレンジして、失敗するのが大事かも!
食育アドバイザーとは?





最後に食育アドバイザー試験の概要について整理するよ。
一つずつ見ていきましょう。
認定機関は?
食育アドバイザーは、一般財団法人日本能力開発推進協会が実施・運用する「食育アドバイザー試験」に合格することで取得できる民間資格のことです。
食育アドバイザー
=一般財団法人日本能力開発推進協会が実施
=「食育アドバイザー資格」に合格することで取得できる民間資格のこと
運用目的は?
その目的は、正しい食の基礎知識を持つ、食育のスペシャリストを育成することです。
正しい食の基礎知識を持つ食育のスペシャリストを育成し、食を通したコミュニケーション能力の程度を審査し、証明することにより、職業能力の向上と社会的経済的地位の向上に資することを目的とします。
引用:一般財団法人日本能力開発推進協会受験概要



自分とその家族はもちろん、特に子どもを健康的に育てるために役立つ知識が体系的に学べるよ。
| 食育アドバイザー | |
|---|---|
| 受験資格 | 認定講座で全カリキュラムを修了した者 |
| 講座料金 | 38,600円 |
| 学習期間 | 3か月 |
| 学習内容 | 食育の基礎知識 食品の安全性についての基礎知識 食育活動について 上記に付帯する基礎知識 |
| 受験料 | 5,600円 |
| 合格基準 | 得点率70%以上 |
| 合格率 | 非公開 |
食育アドバイザーは独学できる?
食育アドバイザーは、独学のみで取得することはできません。



受験資格は、「認定講座で全カリキュラムを修了した者」。必ず認定講座を受ける必要があるんです。
合格基準と合格率は?
食育アドバイザーの試験は、自宅で受けることができる「在宅試験」であり、テキストを見ながら受験可能です。
合格基準は、全問題の合計点数の70%以上の得点があれば問題ありません。
そのため、他の民間資格と比べても難易度は低いと言われています。
万が一、不合格でも、再度勉強して何回でも受験できるので、真面目に勉強していればいつかは合格・取得できる資格です。



なんという安心感!笑 合格できないかも…と心配される方にとってはうれしいよね。
食生活アドバイザーを取得した芸能人
食生活アドバイザーを取得した芸能人は、以下の方々です。
・はんにゃ川島さん
・新山千春さん など



芸能人のみなさんも、合格おめでとうございます!!
まとめ:食育アドバイザーは意味ない?仕事に役立てる方法を解説!


食育アドバイザーは役立たないわけではないですが、就職や転職、キャリアアップなどの仕事につなげたい人にとっては、あまり向いている資格ではありません。
意味ない&役に立たないと言われる理由は、以下の3つです。
民間資格のため信頼性は高いほうではなく、そんな民間資格の中でさらに専門性が弱いので、食育アドバイザーだけで仕事を得るのは若干難しいというのが本音です。
また、資格取得者限定のサービスなども少ないので、とって終わりになりがちです。
しかし、それでも食育アドバイザーをとって仕事に役立てたいなら、少なくとも以下の3つについては整理しておきましょう。
組み合わせるための資格として、発酵をテーマに選ぶのもおすすめです。
民間資格ではありますが、発酵ライフアドバイザー養成講座は、講師養成講座を無料で受けられたり、資格取得者限定のコミュニティで行われる勉強会に参加できます。
参考にしてみてね。
発酵を体系的に勉強したくなったら…
発酵ライフ推進協会オンライン校へ
\仕事に繋がる無料サポートもたくさん(*´ω`*)/